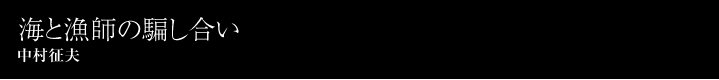![]()
2009.07.20
ハマグリの記憶が蘇った、4年前の夏
高知県の最東部。徳島県に接して甲浦(かんのうら)はある。平安時代、紀貫之が『土佐日記』にも記した古くからの湊町だ。
旧暦3月14日、大潮の日。徳島空港から海辺を南東に走って2時間──甲浦の白浜ビーチに着いた。
桜の花はまだ残り、みどりの葉も萌えだしている。光が浜に撥ね、風がTシャツを心地よく揺らしていく。浜のすぐ近くまで小高い山が迫り、2本の小さな川が注ぎ込んでいた。
阪本五月さん(28歳)はこの浜で育った。
いまは神戸で看護師をしているが、週末には甲浦に戻ってダイビング関係の仕事も手伝っている。
海が好きなのは祖母譲りだ。
「泳ぎを覚えたのもこの海なんです。プールもあったんやけど、授業は海。小っちゃかったんで、浜はもっと大きかった。友だちはもちろん、祖母や母とも遊びにきました。春の大潮の日は必ず海に行くんです。母は磯でヒジキを採ってくれ、祖母は岩牡蠣をとってくれる。岩の裏側にクロベって小さな巻き貝がポロポロ引っ付いてたり。磯遊びが終わると、みんなでハマグリ拾い。夏になると、父と兄が海に潜って、トコブシやサザエでバーベキュー。海で遊ぶのは家族の定番行事やったんです」
白浜は遠浅で有名だ。潮が引くと、汀線は50メートル近く沖へ移動する。水が引いたばかりの砂地は淡いカフェオレ色だ。波が静かに寄せては返し、透きとおった水が春の光にきらめいている。水辺を歩くと、小魚がさっと逃げていく。
「4年前に母と久しぶりに磯遊びに行く途中、浜をちゃぷちゃぷ歩いていたんです。そしたら足の裏につるんとしたものが当たった。石はザラザラしてるけど、ハマグリはつるっとしてるんです。それを指先に感じて。で、ゴボッと拾い上げたら、やっぱり、ハマグリやったんです」
ハマグリはもういないかもしれないと思っていたのに、拾い始めると、意外にもたくさんいて、驚いたそうだ。
その日から、再びハマグリのことを意識し始めたのだという。
「足を8の字を描くようにして探すんです」
干潮は午前11時40分。
今日は祖母、母と久々に三人一緒の潮干狩りだ。
祖母の前田民枝さん(80歳)は杖をつきながら浜に下り、熊手で砂地を掻いて貝を探している。 「砂に潮吹きの穴あいてるんやね。そこを掘ったらええねん。耳澄ますと、ハマグリの音もするんよ。潮吹く貝の音やね。昔はようけおりましてん。けんど、この頃はなかなかおりませんわ。いま頃は海に行てみぃきんね、おるかおらんか、わからん」
そう言いながらも、ちょっと空を仰いで、晴々とした顔で笑った。 「お祖母ちゃん、昔から、海、好きやからなあ」
五月さんが眩しそうな顔をする。 「貝おる言うたら、皆がざーっと来ますやろ。ほんで、すぐなくなるんやね」とお祖母ちゃん。五月さんは膝辺りまでザブザブと海に入っていき、ツイストを踊るように腰と両脚をくねくね動かしている。
「足を8の字を描くようにして探すんです」
誘われて、ぼくも海に入った。
水は想像していたよりも冷たい。
五月さんの動きを真似てハマグリを探す。
と、足がどんどん砂にめりこんでいく。粒子が細かいのだろう。感触がとてもやわらかい。砂が海に舞い、透明な水が濁る。右足が足首まで入って動きにくくなったので、今度は左足で探してみる。
「あった! 一個ゲット!」
突然、五月さんの声がした。探し始めて、ものの5分も経っていない。やはり子どもの頃からの訓練の成果だろうか。
するうち、また「あった、あった」と笑い声がした。
お祖母ちゃんとぼくは黙々と貝を探し続ける。
雲一つない空には鳶が輪を描いている。
採り始めて30分──。母の阪本菊江さん(60歳)もタオルを首に巻き、手製の籠を持ち、ハマグリ・ツイストを踊っている。籠は採った貝を入れておくためのもの。中に小さなハマグリが2個入っていた。
「今日は小さいのばっかりで……」
ちょっと恥ずかしそうに微笑んだ。
「浅い所は先月の大潮のときにみんな採ってしもたかもしれませんね。やっぱり深い所がようけ採れます。夕方になって潮が満ちて、誰もいなくなったときに水中眼鏡をして潜ってみると小指くらいの穴が開いてる。そこを掘ると大きなハマグリが必ずいるんですよ」
五月さんはすでに15個ほど採っている。その秘訣は何だろう?
「一個採れたらちょっと横移動するんです。すると、必ず近くに何個かいますよ」ツイストを踊りながら言う。
「こんな感じで、つるんと……」言うが早いか海中に手を突っ込み、「ほらっ!」
掌には殻の幅6センチのハマグリが載っていた。
美しい居場所を求めて、浜から浜へ移動するハマグリ
現在、日本の市場に出回る90%以上が輸入ハマグリだという。日本在来種は絶滅が危ぶまれている。そうした状況のなか、甲浦では白浜ビーチのみならず、その南西にある生見(いくみ)ビーチでもハマグリが元気に生きている。
甲浦の伊勢エビや貝で生計をたてる漁師・森本浩一さん(55歳)に話を訊いた。
「ハマグリは浜を耕してくれるんやな。そやからハマグリのある浜はきれいや。砂がやわい。固うないんよ。足首までもぐるし、手ぇ入れたら、ぷすっ と入る。形かて、ハマグリは自然に沿うてるわな。砂に入りやすい流線型になっちょる。そやから、逃げるんも、めっちゃ速い。ハマグリは浜になじまんかったら、すぐ移動するきぃな」
どうやって移動するんですか?
「ねばねばした紐みたいな粘液出してな、それを帆にして、潮の流れに上手に引っ張られて移動しよる。ほんで、自分好みのきれいな浜に来る。だいたい、白っぽい砂の所やな」
森本さんはずっと甲浦でエビや貝の漁をしてるんですか?
「おうよ。自分の地先で飯が食える漁師は最高やがな。地先がなかったら漁師やないでぇ。高いガソリン焚いて遠い海まで行くより、近くで暮らし立てられた方が、そら、ずっとええやろ。地先は自分の地盤や。守りたいわな。漁師は浜から始まったわけやろ。最初は地先から始まって次第次第に大きゅうなって、やがて沖へ遠洋へと行きだしたんや。基本は足もとやがな。地先が大切なんや」
ハマグリで結ばれる三世代の絆
五月さんとお母さん、お祖母ちゃんが採ったハマグリを自宅の庭で焼いてもらうことになった。
山裾にある家の庭には水仙の芳しい香りが流れていた。ツバメがひょいと電線をかすめて飛んでいく。
七輪に炭火をおこし、網の上にハマグリを載せる。縁側にお祖父ちゃんも出てきた。
ハマグリはしばらくじっと蓋を閉じたままだったが、やがて、ぶくぶくと貝の中の塩分が泡立ち始めた。ときおり炭火がはぜると、七輪を囲んだみんながワッとのけ反り、笑いがおこった。
そしてまた、みんなの目がハマグリに戻る。
鳥の声が聞こえる。
蜂の羽音が聞こえる。
やわらかい風が吹いている。
夕暮れの光が斜めに射している。
ハマグリの殻の焼ける匂い、潮の匂い、炭の匂いが混じり合っていく。
ハマグリの殻が開くのを待つこのひととき。幸せな静けさにみんなが包まれている。
そして、その中心にハマグリがいる。きっと、ハマグリがみんなを結びつけてくれているのだ。
焼ハマグリを食べさせてもらった。
内臓が透けて見える身肉は、プリプリとはち切れそう。こんなハマグリを見たのは始めてだ。白浜の海が形となって、今ここに存在している。
まずは、貝のエキスと潮が混じった汁を殻から直接飲む。
と、濃い海の味が口の中にむわっと広がった。薄っぺらではない、懐の深い塩味だ。
身肉をはふはふ食べる。
弾力があって、なかなか噛み切れない。いままで食べていたハマグリがまるでブロイラーのように思えてくる。
口の中は砂でジャリジャリするが、この砂がハマグリを育ててくれたのかと思うと、そのジャリジャリすらも美味しいのだ。
ぼくは、結局、一個もハマグリを採ることはできなかった。
だから五月さんとお祖母ちゃん、お母さんが拾ってくれたハマグリをいただいている。ありがたいことだ。でも、自分が採ったハマグリを食べていれば、もっと美味しかったかもしれない。
いや。そんな贅沢を言ってはいけない。足もとの幸せとは、足るを知る幸せなのだ。
蜃気楼の語源は、大ハマグリ(蜃)が海中を移動するときに吐き出す粘液によって、たちあらわれた楼閣のことだそうだ。
願わくば、ハマグリの日の幸せが、そして、地先に輝くきれいな海と人が、蜃気楼でないことを。