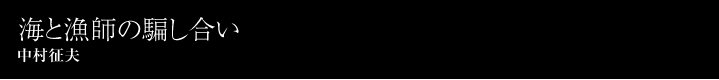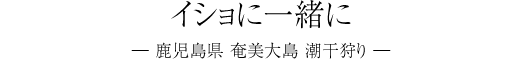![]()
2010.07.14
漁のない日はイショで潮干狩り
イショとは奄美の言葉で「磯」のこと。
磯で魚や貝や海藻をとることも「磯」という。
奄美大島の北西部。喜瀬集落に住む柊田謙夫(ふきだ・けんお)さん(66歳)は、漁協組合長もされている一本釣りの漁師。
ふだんは長男と二人で漁船に乗り、喜瀬から2時間あまり沖合でシロダイやアオダイ(ホタ)を釣っている。長男は高校卒業後、東京で約20年間、美容師をやっていたが、昨年末に奄美に帰ってきた。
「年をとると漁師の仕事を教えることができんようになるから、いまのうちに早く帰ってこいって言うたんです」
漁のない日は謙夫さんは奥様の洋子さん(64歳)と一緒にイショに行く。つまり潮干狩りである。
喜瀬には奄美で最も大きな干潟が広がっている。旧暦3月29日、大潮の干潮時(ちょうど正午すぎ)、柊田さん夫妻を喜瀬干潟に訪ねた。
貝の居場所を「叩いて」探す
「この前、梅雨入りしたばかりなんだけど、今日はよく晴れたよ」
麦わら帽を目深に被った謙夫さんが白い歯を見せて空を仰ぐ。
雲一つない青天。風が心地いい。湿気の多い奄美には珍しく、からっとしている。
堤防を越えると、沖まで干上がった渚の景色がそこにあった。
謙夫さんは長靴を履き、作業用の服とズボン。タオルで顔を覆うようにして、右手には竹の杖。左手にはトンボ──野球グラウンドなどを整備するときに使うTの字になった木の棒。腰にはテルといわれる竹籠を下げている。これが奄美の潮干狩りスタイルなのだという。
その竹の杖はいったい──。
「これ? 仕込み杖。嘘、うそ(笑)。
でも、座頭市方式で、石ころの多い所をこれで、コンコン、コンコン、叩いて回るんです」
叩く……?
「叩くとね、貝がびっくりして、ピュッと潮を吹くんです」
なるほど。それで貝の居場所がわかるのだ。
で…もう片方のトンボは?
貝の居場所を「ならして」探す
「このトンボ(こっちでスリシャって言うんだけど)を引いて干潟をならしていくと、じわっと水が染み出てくるポイントがあるんです。そこが貝のいる所。砂地は広いし、どこに貝がいるかわからんから、スリシャを引いて効率的に発見するわけ」
よく考えたものだ。昔からこういうやり方で貝を見つけていたのだろうか?
「いえいえ。スリシャを使うようになったのは7~8年前かな。高校生たちがこれを引いていたんだよ。
最初は、何してるかわからんかった。で、見に行ってみると、バケツ一杯の貝を採っていた。『どうやって採るんだろ?』と観察したわけさ。すると、スリシャで引いていくと、干潟からピュッと貝が潮を吹いた。そういうことかと納得して、私もスリシャを使いはじめた。
昔は、杖もなかったんだよ。これも使いだして14~5年経つかなあ」
それまではどうやって採っていたんですか?
「足をハの字にして、干潟の中にもぐらせ、ぐりぐり動かして貝を探ったもんさ」
高知・甲浦(かんのうら)でハマグリを採っていたあのやり方だ。
「この辺りの人は先月からここで潮干狩やってるから、今日は貝がいないかもわからんねえ。女の人たちがしょっちゅう採りにいってるからね。
さあ、座頭市やって、いっぱい採らんとよー」
麦わら帽子を被り直し、謙夫さんは竹の杖で干潟をコンコン叩きながら歩きはじめた。
干潟に三つの穴が見えたら、「生きた化石」といわれる「ミドリシャミセンガイ」
「いた、いた!」
声がしたので、そちらに歩いていくと、長男の圭一郎さん(42歳)がしゃがみこんで、両手で干潟を掘り返している。
覗き込んでみると、何やら太めのモヤシみたいなものが見える。見方によってはナメクジのよう。ちょっと気味が悪い……。
「ミドリシャミセンガイです。この管を無理に引っ張るとちぎれるので、周りの土を掘って貝の本体を取り出すんです。でも、潜るのが速いから、素早く掘らなくちゃならない」
20センチほど掘って、やっと貝を取り出した。ゴキブリみたいな色と形の殻から、モヤシの親分がちょろっと出ている。三葉虫みたい。やっぱりグロテスクだ。こんなの、食べられるのだろうか……。
「トンボで引いて、干潟に三つ穴が見えたら、この貝です。こんな色と形ですけど、コリコリして美味しいんですよ。湯がいておつゆにしたり。昔はいっぱいいたんですが、今はここと隣の手花部(てけぶ)の干潟にしかいないです」
じつはミドリシャミセンガイは貝類(軟体動物門)ではなく、腕足動物門という別のジャンルに入る。カンブリア紀にあらわれて、古生代に栄え、「生きた化石」といわれる貴重な貝だそうだ。有明海周辺では女冠者(めかじゃ)といわれ、煮付けや塩ゆで、味噌汁などで食べられているという。
「自分が捕ってきたものが、お家の晩御飯になるのがうれしかった」
「泳ぎを覚えたのもこの海です。満潮になると今より2メートルほど海面が高くなる。干潮は潮干狩り、満潮は海水浴──高校卒業するまでずーっと、海が暮らしの近くにありました。
子どもの頃は毎日友だちと一緒に海に行って、貝や魚を捕ってきました。この干潟には川が2本流れ込んでいますが、そのうちの1本が自宅の裏を流れていて、そこでテナガエビやウナギを捕ったり。自分が捕ってきたものが、お家の晩御飯になるのが何といってもうれしかったですね」
東京にいるころ奄美の海がとても恋しかった、と圭一郎さんは言う。
ぼくも生まれ故郷の大阪の海が恋しい。いくら汚れてしまった海でも、いや、汚れてしまったからこそ恋しいのかもしれない。
少年時代を過ごした1960年代の大阪には、まだ白砂青松の浜があり、干潟も藻場もあった。朝、兄が捕ってきたアサリを味噌汁の具にしていたし、天秤棒を担いだオバさんが捕れたてのシャコを売りに来たりもした。今は臨海工業地帯になってしまった大阪湾にも、海とつながる暮らしがあった。
きっと兄も、自分がとってきたアサリが食卓に上り、家族みんなが食べるのを誇らしく思っていたのだ。圭一郎さんの話を聞きながら、初めてそのことに気づいた。
今、埋め立てられた大阪の海は、物理的にも心理的にも人から遠く隔たってしまった。
干潟に小さな二つの穴は「カワラガイ」
シャバシャバという音をたてて潮が満ちてきている。そのスピードは驚くほど速い。海から顔を出す干潟がどんどん狭まっていくのがわかる。浅瀬に足を踏み入れると、小さなハゼの群れが四方八方に逃げていった。
洋子さんがトンボを引いていると、いきなりピュッと15センチほど潮が噴き上がった。
掘り出すと、貝殻の噛み合わせの所がきれいにギザギザになっている。
「殻が瓦で葺いたようになっているから、カワラガイ。干潟に二つ小さな穴が開いているんです。刺さるようにして頭をちょこっと突き出しているのはタイラギ。
干潟は生きものの宝庫。タケノコガイ、マクラガイ、アカガイ…ワタリガニもいるし、2月から3月のまだ寒い頃はアオサのみどりもきれいです。アオサは天ぷらや鶏のスープが美味しくてね。タナガ(テナガエビ)は潮が引いていくときが一番捕れます。素揚げやボイルにするんです。
昔はちょっと沖の方に行くと、モズクも生えよったけど、今は採れんですね。シラヒゲウニもたくさんおったけど、おらんしね。
冬場は夜の潮干狩があるんです。こっちではイザリって言います。懐中電灯もって銛もってね。スガリ(小さなタコ)を突いたり、サザエやトコブシを捕ったり。エビは小っちゃくても目が二つ光るんです」
旧暦の3月3日は「浜下れ」の日。ネリヤ・カナヤの神さまに感謝する
一年で一番潮の引く旧暦の3月3日。奄美には「浜下れ(はまおれ)」という行事がある。
30年ほど前までは、学校では下校時間を早め、役場や会社では午後は誰もいなくなり、集落の人みんなが浜に下りたのだそうだ。
謙夫さんは言う。
「昔はそれぞれのお家で重箱にごちそうを詰めて浜に下りたもんです。20名くらいで輪になってその重箱を交換して食べたり、焼酎のんで、三味線弾いて、歌ったり踊ったり。タコや貝を採ってくる人もいるし。夜までみんなで飲み食いする。そりゃ楽しいさ」
以前ほど「公的」なものではないが、「浜下れ」は今も脈々と続いている。
奄美や沖縄では、海の彼方に「たましい」のふるさと(常世・とこよ)があると考えられていて、沖縄ではニライ・カナイ、奄美ではネリヤ・カナヤと呼ばれる。
幸せ(五穀などの食べ物や生命)もネリヤ・カナヤからやって来るし、先祖のたましいはネリヤ・カナヤに戻って、神々になっている。そうした廻る生命の源泉としてネリヤ・カナヤがある。
「浜下れ」はネリヤ・カナヤの神さま(たましい)と共に飲食し、歌や踊りで神さまへの感謝の思いを伝えることから始まった。
集落の前に広がるイショ(磯=海)は、神と人とが一緒に遊ぶ大切な広場なのだ。
海が暮らしのすぐ側で、人をやわらかく包むように生きている。
波や潮の満ち引きは、海の呼吸だ。
その息吹(いぶき)の聞こえる干潟が、五月の光に眩しく光っていた。