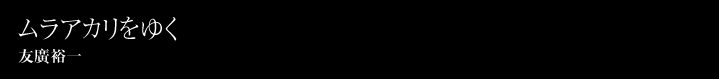![]()
2011.04.08
「弱冠26歳の若者です」
はじめまして。これから筆を取らせていただくことになりました、友廣裕一と申します。
現在26歳。ここに名を連ねられている方々に比べると、年齢も器も小さい若輩者ですが・・・
日本中の地域を自分の足で歩き、目で見て、出会った方々と言葉を交わす中で受け取ったものを、飾らない等身大の言葉で誠実に書かせていただければと思っています。今回はまずプロローグとして、自分が何者なのかということから綴ってみたいと思います。少々長くなってしまいますが、軽い気持ちでお読みいただけたらと思います。
「言葉を交わす」旅を続けたい
ぼくは2009年2月、東京で住んでいた1人暮らしの家を引き払い、日本一周の旅に出ました。それから約180日間、主にヒッチハイクをしながら、全国70以上の地域を訪ね、それぞれの土地では民家に泊めてもらい、第一次産業(農業、林業、漁業、畜産業・・・等)を中心としたお手伝いをさせていただきました。その土地に根ざした暮らしや仕事に触れながら、どんな人たちが、どんな想いで生きているのかを感じたかったから。これからそういう地域に関わる仕事をしたいという想いもあり、そのような人生につなげる旅でもありました。この旅を思いついたとき、はじめは旅に必要な資金を稼ぐことを考えたのですが。そんなときに、ふと気づいたこと。それは、お金を使って移動して、お金を使って泊まっていては、なにも言葉も交わさずに旅ができてしまう。でもそれでは自分が得たいと思っているものがこぼれ落ちてしまうのではないか――。いろいろと考えた末、その当時自分が持っているものだけで行けるところまで行ってみようと決めました。そして旅を終えてしばらく経った今、たくさんの方々にお世話になりながら旅をさせていただけてよかったと心から思います。
どんな地域にも「アカリ」を求めて……
この旅、この小さなプロジェクトには「ムラアカリをゆく」という名前をつけました。いろいろ悩んだのですが・・・当初は限界集落と呼ばれる地域を中心に訪ねさせていただこうと思っていました。(※「限界集落」とは過疎化などで人口の50パーセント以上が65歳以上の高齢者になり、冠婚葬祭など社会的共同生活の維持が困難になった集落のことを指す)詳しい経緯は後述しますが、それまでの数少ない経験から、いわゆる限界集落と呼ばれている地域にも「アカリ」はあるはずだという仮説が自分にはありました。それは暮らしの中にあるかもしれないし、一人ひとりの心の中に眠っているかもしれないけれど、そこに寄り添えば必ず見つけられるという確信があって。なにもないと言われるところにも、なにかあるんだと伝えたかった。たとえ今は燻って見えにくくなっていたとしても、たしかにそこに輝く「アカリ」を照らし、照らされるような存在になりたい。そんな想いを込めて、ふと頭に浮かんだのが「ムラアカリをゆく」という言葉でした。まだ見ぬ未来に期待と不安を抱いて眠れなかったあの日を思い出すと、ちょっと胸がキュッとなります。
ITバブルの潮流の中で感じた物足りなさ
「なぜそんなことしようと思ったの?」と、よく聞かれます。いつも言葉に詰まるのですが…今回は、ちょっとさかのぼって書かせていただきます。
ぼくは26年前、大阪の片隅のそこそこ便利なベッドタウン的な町で生まれ育ちました。小さな頃はまだ近所に田んぼや畑もあって、友達と一緒に近くの山まで自転車で虫取りに行ったりもしていて。住宅地の中の公園の木にもよく登っていました。しかし小学校も高学年になると、近くにあった川は埋め立てられて、いつも遊んでいた空き地は住宅地になった。いま思えば、どんどんアスファルトで敷き詰められていく町並みとともに、自分の興味も都会化していっていたような気がします。当時はそれでも自分なりに楽しみを見出して、その時々にやるべきことを見つけて、与えられた環境に順応しながら日々一生懸命生きていたのですが。地元の高校で部活に明け暮れる日々をすごしたあとは、ビジネスを学びたいと思って東京の大学に上京しました。
商学部に入学した当時はITバブルの全盛だったこともあり、入学して間もなく、机上で経営学を学んでいるよりもリアルな現場を体感してみたいという思いが沸いてきて。そんな時、たまたま起業するという先輩に声をかけてもらい、会社の立ち上げからしばらく手伝わせてもらいました。大学1年生の終わりから実質的には約半年間くらいでしたが、ビジネスの面白さやスピード感の一端に触れるにはこれ以上にない経験だったし、自分の将来を考えるには示唆に溢れた素晴らしい時間でした。この経験を元に、自分が大切にしていきたい価値観というのがおぼろげながら見えてきました。この頃は、ITという間接的なものでは物足りなくて、もっと「人」に関わる仕事がしたいと感じていた気がします。
高野孝子さんとの出会い
その後、「社会起業家」と呼ばれる人たちに傾倒し、彼らを支援するような活動の事務局として関わったあと、「持続可能性(Sustainability)」という概念に出会いました。この言葉に、なんだかすごく惹かれるところがあって。「あーこれこれ」と。当時は分かったような分からないような妙な納得感を胸に抱えて、興奮しながら本を読んでいたのを思い出します。それがちょうど大学4年生になるタイミングで、この言葉を探しながら講義要綱をパラパラとめくっていました。そこで出会ったのが「持続可能な社会と市民の役割」という講義。当時「持続可能」という言葉が講義名に入っているのはこれしか見つけられなくて。受講を即決する理由としては十分でした。かつて犬ぞりとカヌーだけで北極海を横断され、環境教育の現場に立ち続けられてきたNPOエコプラス代表の高野孝子さんが教鞭を執られる1年間の講義でした。これは一味もふた味も特色のある講義で、特に印象的なのは、夏に行われたミクロネシア連邦ヤップ島での2週間弱の実習。ヤップ島といえば石貨が今でも貨幣価値を持っていることでも有名な島ですが、地元のローカルコミュニティに入れていただき、自給自足にほど近い暮らしをする機会を得ました。村中の子どもたちは朝から晩まで5歳児から高校生くらいまでが一緒に遊んでいて、海に飛び込んではキャッキャと言いながら駆け回っていて。朝は筏に乗って沖で漁をして、のどが渇いたらヤシの木に登ってココナッツを割り、森を歩けばフルーツがいっぱいで抱えきれないことも。夜中に動き出す大きなカニを子どもたちとつかまえて、主食のバナナとタロイモを調達してきてはヤシ殻を燃料にして料理をつくる。大阪で生まれ育ち、東京のアパートで1人暮らしをしていた自分には想像もつかない世界でした。
ヤップ島での気づき
中でも大きい気づきは、この間まったくお金をさわらず、時計もまったく見なかったということ。物心ついたころから時計の刻むリズムに合わせて生活をしてきて、お金の量と生活の豊かさは比例すると、なんとなく信じ込んでいた。でもヤップ島で生活してみてはじめて、それが絶対的なものではなかったことに気づいたのでした。もちろんお金がいっぱいあって、早い時間で多くの作業を終えれることは、リスクを低減させて余暇も生み出せるということ・・・。これはたしかにある豊かさを実現する手段の一つだったのかもしれません。でも本当の豊かな暮らしと、この手段との間には因果関係があるようでなかったりもすると知りました。少なくとも一日1ドル以下の所得で、いわゆる貧困地域と定義されているはずのヤップ島には、毎日おいしい食事と笑顔が溢れていた。暮らすためだけに一日のほとんどを費やす生活は、たとえ食べるためにクタクタになろうとも、ぼくの目には豊かな暮らしだと映たのです。
自給自足の実感と満足感
ヤップ島から帰国した後、東京の暮らしに戻ると、周りの同級生は就職の準備に追われていました。そんな中で就職活動をしなかった自分だけ「豊かさとはなにか」という別次元の問題を抱えて悶々としていました。いま思えばただの笑い話ですが(笑)当の本人はいたってまじめに悩んでいました。いろいろなことを考えては都会、つまりは自分のこれまでの人生を否定しようとしたりして。そうこうしているうちにも卒業は迫っていて。ああでもない、こうでもないと葛藤しながら、自分はどうやって働いて生きていくのか。それが見えなくて、なにが正しいのか、自分にはなにができるのか分からず、ただもがいていました。
そんな時、高野孝子さんが関わられている新潟県南魚沼市の清水という集落に連れて行ってくださったのでした。山梨との県境近くの峠の麓に位置する15軒ほどの小さな集落です。さわやかな秋晴れのもと、ソバを収穫したり、山の間伐を手伝ったりしながら、中山間での暮らしの一端に触れた初めての機会でした。それから何度も通い、卒業してから知り合いの人と会社を立ち上げて働いていた頃も含めて、ことあるごとに訪ねさせてもらっていました。中山間地なのでビジネスとしての農業が成り立つような農地はないけれど、各々が小さな土地で暮らしとしての農を実践している。そこではシノシシやシカなどの獣の肉が普通に食卓に並び、山菜も米も野菜も、自分が食べるものくらいは皆が自給していることに気づいた。これにはジンワリと驚きました。
冬は4メートルの雪が積もり、国道が通るまでは陸の孤島と呼ばれて村から出ることはできなかった。そんな中でも数百年前から人々を生きながらえさせて来たのは、洗練された保存食の文化だということも知った。ここには山伏と呼ばれる修験者の修行の場があるのですが、「男になるなら滝行には行くべきだ」と言われて、2月の雪山で滝行へ一緒に参加させてもらったり、夏は火渡りに混ぜてもらったりして。今まで知る由もなかった中山間の暮らしに触れさせてもらった。いつだって帰るときには温かい気持ちで心がいっぱいに満たされていて。「おいしかったなー。たのしかったなー。きれいだったなー。かっこよかったなー。やさしかったなー」って、ポジティブな感情で満たされて。そして「あぁ、また行きたいなー」って純粋な気持ちが湧き上がってきた。だからまた行く。約1年間はそれを繰り返していました。
「限界集落」報道に対する強い違和感
あるとき東京にいると、中山間地域が語られる文脈には、ネガティブな情報が多いことに気づいた。ぼくが通っていたこの清水集落のようなところが「限界集落」と呼ばれていることも知り、この言葉を通じて医療とか教育とか後継者について問題だといる情報が届いてくる。でも、これが自分の出会っている地域のそれと同じものとは到底思えなくて。それは客観的な事実としては正しいかもしれないけれど、そこから想起されるもののイメージがまったく違う。色褪せて冷たくて悲しい限界集落のイメージは、あの鮮やかでやさしくてあたたかい村のじいちゃん・ばあちゃんが住んでいるそれとはまったく違うものだった。大雪が積もる中で生き抜いてきた暮らしの知恵には、とても多くの先人の知恵や技術が積み重なり、洗練された文化として眠っている。それらを大切に受け継ぎ、手間と時間をかけて自然の恵みをいただく丁寧な暮らしが、都会のボタン一つで事足りる社会より劣ったものだとはとても思えなくて。ぼくはこの経験を友人に話していた。すると、みんな決まって「行ってみたい!」という反応をしてくれる。そして連れていくと、決まって自分と同じような反応をしてくれて、そこからなにかが変わっていくような感覚もあった。「問題ですよ」と喧伝することもいいけれど、それではほとんどの人は動かないし動けない。それは自分も同じで。だとすれば「いいところだよ」というメッセージの方が、事実を動かす力があるんじゃないか。だから、アカリを伝えよう、と。<事実>は視点の当て方次第で、いかようにもとらえることができるはずだから。
「ムラアカリ」の先に、未来のアカリが広がる
このような経験を経て、文頭の旅につながりました。一筆書きの旅は180日間。北は北海道から南は沖縄まで70以上の町村を訪ねたところで終えましたが、その後の動きも含めれば、軽く100地域以上にご縁をいただきました。そこからつながりで、現在は様々な地域で役割を与えてもらって活動しています。まだまだ自分にできることは限られていますが、こうして言葉を通じて自分の経験を伝えるようなこともあれば、離島の漁業振興であったり、「食育」を軸に都会と田舎をつなぐ市場を開いたり、田舎の豊かさを感じる小さなツアーを企画したり、地域に住む方々が自分たちのアイデンティティを再発見するようなフォーラムを企画したり、地域とつながる仕事を志す人たちに向けた学びの場をつくったり。おかげさまで今もまだ旅の延長線上に立っているような感覚で働き、暮らしています。このような流れの中で、今回は「日本の知恵プロジェクト」でも連載をさせていただくことになりました。ここでは、地域に根ざして、そこに灯るアカリのように暮らす「人」の暮らしや仕事にフォーカスを当ててご紹介していけたらと思っています。今後とも、どうぞよろしくお願いします。