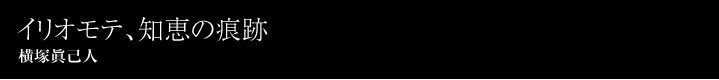![]()
2014.04.25
染めは夏の仕事、糸取りは冬の仕事
 リュウキュウイトバショウ(Musa balbisiana var.liukiuensis):沖縄地方には、自生していなかったが、1500年代に東南アジアから沖縄本島へ渡り、八重山地方に入ったのは1700年代といわれている。
リュウキュウイトバショウ(Musa balbisiana var.liukiuensis):沖縄地方には、自生していなかったが、1500年代に東南アジアから沖縄本島へ渡り、八重山地方に入ったのは1700年代といわれている。
2月に再び石垣昭子さんの紅露工房を訪ねた。冬の西表島は、10度を下回ることはほとんどないが、北東の風が強く、どんよりとした日が多い。ところが、この日は珍しく快晴で、少し動くだけで汗ばむほどの陽気だった。工房では、ちょうどイトバショウから糸をとる作業がはじまろうとしていた。
「染めの作業は夏場が主で、糸取りは冬場の仕事なのです」そう言って、工房から出てきた昭子さんは、長靴に鎌を持った野良仕事スタイルだった。昭子さんの工房には、美大生や染織を志す人たちが研修生として絶えず出入りしている。そんな彼らに「畑に入って、糸を作りましょう」と声をかけると、「えっ糸を作るのですか」という答えが返ってくる。「糸は買うものだと思っていた」という人がほとんどだという。
植物と向き合い相談する
工房の敷地にはイトバショウの畑や苧麻(ノカラムシ)、染料をとるためのインドアイやヤエヤマアオキなども植えられている。昭子さんは、糸も染料も畑や庭で育て、さらに野山の植物も使って作品を作り上げている。自然のサイクルの中で植物と向き合うことが基本なのだ。植物の枝も樹皮も根も、やみくもに切ったり、剥いだりすればいいというものではない。植物との相談が大切なのだと語る。
たとえば、フクギの花がきれいに咲いているのを見て、いい色だと思って使ってみると、想像していたほど染まらなかったことがあった。逆に、花が咲く前だと枝だけでも緑がかった綺麗な黄色に染まった。その時は、「きっと植物は花を咲かせるときに、色を使ってしまうのだ」と解釈した。そんな発見をくり返すことで、しだいに植物と相談ができるようになったそうだ。相談するためには、植物と向き合う時間が必要だ。西表島の自然のサイクルの中で、そうした試行錯誤を経て、昭子さんの染織と稲作文化が融合していったのだ。
ここへ来る研究生たちには、そんなことを伝えたいのだが、それには最低1年はここで暮らす必要があるという。そうしないとこの島のサイクルが分からない。芭蕉の糸をとる時期、藍の時期、フクギの時期など1年を通すことで、植物がいろいろなことを教えてくれる。また、村のさまざまな行事に参加をすることで、暮らしの中から生まれた文化としてトータルに見ることできるようになる。こういうことは残念ながら美術大学でも学ぶことができない。最初は憧れや興味本位でも、理解が深まるにつれ滞在期間が長くなり、工房の門を叩いた人の中には、定住してしまった人も何人かいるそうだ。
一反を織るために100~200本のイトバショウを切り倒す
イトバショウの糸取りは、「荢倒し(うーたおし)」という芭蕉を切り倒す作業から始まる。「荢」とは糸を意味する。荢倒しや野生の紅露(ソメモノイモ)を採ってくるのは夫の石垣金星氏の仕事だ。西表島育ちの金星氏は、芭蕉布を織る祖母のために、小学校の頃によく荢倒しを手伝っていたそうだ。
金星氏と共に畑に行くと、背丈のそろったイトバショウがぎっしりと生えていた。それは手入れをしているからで、イトバショウが生長する5~10月の夏場にかけて、葉を切り落とし高さをそろえる。イトバショウを切り倒して糸取りの作業をするのは、基本的に植物がほとんど生長しない冬場だ。芭蕉布一反を織るためには、100~200本のイトバショウを倒さなければならないそうだが、この日は15本を切り倒していた。
イトバショウの茎は地下にあり、地上の茎のように見える部分は偽茎(ぎけい)と呼ばれ、葉鞘(ようしょう)が巻き重なってできている。その葉鞘の繊維が芭蕉布の糸として利用される。荢倒しのあとは、繊維をとるために葉鞘を剥ぎ取る「荢剥ぎ」をする。荢剥ぎしたものを灰汁で煮込む作業が「荢炊き」。炊きあがったものの不純物を取り除き、繊維だけを取り出す作業が「荢挽き」だ。その繊維を細く裂いていき、一本の糸に紡ぐ「荢績み(うーうみ)」が最後の作業となる。


 左から)
左から)
○荢剥ぎをする石垣さん。荢剥ぎは葉鞘を薄く剥いでいく作業だが、外側の繊維は粗いので、芭蕉布の糸には使えない。この部分は皮芭蕉と呼ばれている。
○皮芭蕉はそのまま乾燥させて、粗い糸を取る。台湾や東南アジアでは、この部分だけを利用して、タペストリーなどを作っている。芭蕉布にする芯に近い部分は、逆に利用されないそうだ。
○八重山地方では芭蕉布で使わない皮芭蕉で、獅子舞の衣装を作る。節祭の獅子舞も皮芭蕉で作られている。



 「荢剥ぎ」(写真左から)
「荢剥ぎ」(写真左から)
○畑から工房へ運び込まれたイトバショウの偽茎。
○偽茎の使えない部分の葉鞘を畑で剥ぎ落としてしまう。葉鞘を剥ぎ落とす様子は、白ネギをイメージするとわかりやすい。
○皮芭蕉を剥いでいき、このくらいから芭蕉布の糸がとれる部分になる。
○芯の部分は食用になる。柔らかく、こりこりとした食感だった。


 「荢炊き」(写真左から)
「荢炊き」(写真左から)
◯芭蕉布の糸がとれるのは、芯に近い部分。
◯荢炊きは芯に近い部分の荢剥ぎしたものを灰汁で煮込む。灰汁を使うという作業は沖縄本島から伝わった技術。こうすることできめの細かい繊維がとれる。東南アジアや台湾では灰汁を使う技術が発達しなかったため、芭蕉布が生まれなかったのだろう。
◯木の種類によって灰汁の力が違う。竹富島ではオオハマボウ、多良間島ではテリハボクが主に使われているそうだ。金星氏によるとマングローブ植物の灰汁には力あるらしい。



 「荢挽き」(左から)
「荢挽き」(左から)
○荢炊きされたものを取り出し、次の作業の準備をする。
○荢挽きは、専用の道具を使って不純物を取り除き、繊維だけを取り出す。イトバショウの手入れで高さをそろえるのは、荢挽きの作業をしやすくするためだった。また、荢炊きがうまくいかないと、この作業に影響が出る。糸作りの工程はすべて繋がっているので、手を抜けないのだという。
○荢挽きに使う道具は、金属製で「パイ」とよばれている。金星氏の祖母はパイに貝を使っていたそうだ。奄美地方の「エービー」と呼ばれる竹製の道具でも実演してくれた。手に馴染めば、どんな素材でも道具になる。
○荢挽きの時の不純物は棄てずに芭蕉紙作りに利用される。祖納集落にある西表小中学校では、卒業証書のための芭蕉紙を子供たち自身が作る。
「績む(うむ)」は「産む」こと
 荢績みでは、荢挽きした繊維の束を裂いて糸にしていく。その太さは自由。作る作品に応じて糸の太さを決める。糸と糸を縒り込んで1本の長い糸にする。宮古・八重山地方は縒り込む方式だが、沖縄本島はでは結ぶ。紡ぎ方で、どこの地方の芭蕉布か判断できる。
荢績みでは、荢挽きした繊維の束を裂いて糸にしていく。その太さは自由。作る作品に応じて糸の太さを決める。糸と糸を縒り込んで1本の長い糸にする。宮古・八重山地方は縒り込む方式だが、沖縄本島はでは結ぶ。紡ぎ方で、どこの地方の芭蕉布か判断できる。
荢績み(うーうみ)はかなりキャリアを積まないとできない手業だという。ただし、覚えてしまえば勝手に体が動くので、おしゃべりをしながらでも、テレビを見ながらでもできるようになる。昭子さんのお母さんは100歳まで生きたそうだが、入院中に暇で手が寂しい時は、糸紡ぎをベッドでしていたそうだ。手作業の糸紡ぎはリハビリにもいいという事で続けていたら、若い介護士が興味を持ち、お母さんに教わるようになったそうだ。
荢バーラーと呼ばれる竹の籠に糸がたまったら、ようやく織りの作業に入ることができる。一反分の糸をためるのに、2~3年かかるそうだ。ここを訪れた研究生たちは、みんなすぐに機の前に座りたがるが、「機織りの作業に入ったら、すべての行程の90%は終わっている」と話すと、みんなキョトンとして意味不明の表情を浮かべてしまうそうだ。それは無理もない。植物との対話から糸作り、染めの工程を実際に見ないとその意味は理解できない。布は見えても、見えない部分というのが本当の仕事であるということだ。
荢績み(うーうみ)で糸は完成するが、「績む」を「産む」にかけて、産まれることなのだと昭子さんは語る。「産む」という言葉は女性を象徴するものだ。染織の材料である糸も染料も、地球の大地から生まれる。すべて「産む」という延長線上に繋がっていく。
手の中で績まれていく糸を見ていて、地球という大きな母体の中で生かされているというイメージが脳裏を巡った。