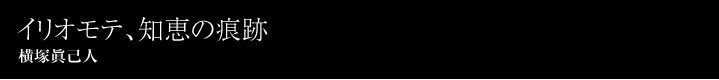![]()
2014.06.20
藍を染めるには、水道水でも海水でもなく、山の水がいい
紅露工房の玄関前に、ユウナの木が枝を広げて木陰を作っている。その根元に、4つの藍瓶が置かれていた。工房から泡盛の一升瓶を抱えて出てきた石垣昭子さんは、おもむろに藍瓶のふたを開け、その中に一升瓶の中味をそそぎ込んだ。瞬間、あたりに泡盛と藍の濃厚な香りがただよった。瓶の中をのぞき込むと、盛り上がった気泡が見えた。「藍の花です」と昭子さんの声が聞こえた。
昭子さんの工房では、天然藍の原料であるインドアイとリュウキュウアイが栽培されている。葉のついた枝ごと山から引いた水に長時間つけ置いたあと、石灰を入れると泡がたち、沈殿物ができる。その沈殿物を藍瓶に入れて染料とする。
山の水を使うのにはわけがある。染色において水と染料植物には相性があるからだ。例えばフクギで染めるときは、石灰が含まれている水道水がいい。マングローブは、海水を使って煮出すと美しく染まる。藍の場合は、中性である山の水がもっとも適していている。
藍の生成は葉に含まれるインジカンがインンドキシルという物質に変化し、それが酸化するとインジゴが生成され、布を藍色に染めることができる。水と植物の相性にしても、藍の生成過程においても、いずれも化学の世界だ。染料は試験管の中で簡単に生成できるので、現実に化学生成された染料が広く使われている。しかし、昭子さんの染料作りを見ていると、化学式の世界だけでは説明のつかないものの存在を感じる。
染料は「作る」のではなく、「育てる」
天然の藍の染料には藍色の他に赤色などいくつかの色素が副成分として含まれていて、化学染料では決して出せない複雑な色合いがあることがわかっている。それは、染料は「作る」のではなく、「育てる」という昭子さんの言葉の中に答えがあるような気がした。毎日、泡盛や黒砂糖などの栄養源を与えて発酵を促すことで藍の染料を大切に育てていく。やがて、発酵が進み液面に藍色の泡が立ってくる。それが藍の花だ。目の前で、当たり前のようにさいている藍の花だが、これをさかせる事はかなり熟練を要する作業で、簡単ではないようだ。昔から伝わる手法どおりにやっても、藍の花がさかないときもあり、完璧だと思っても想像していたほど発色しなかったこともあるのだという。藍瓶のふたを開けて、「気泡がプチプチと消えていかないものは、もっと栄養が欲しいというサイン」「この花は気泡が盛り上がっているし、泡が細かいから元気」「これは色が濃いし、しっかりと発酵している」と藍の花のようすを毎日見ながら世話をする。
味噌も藍もユウナの木の下に置くと発酵が早くなる
昭子さんは、藍瓶の中の発酵菌を育てるために、もう一つユニークな試みをしていた。それは、藍瓶をユウナの木の下に置くことだった。竹富島の実家で暮らしていた時代に、彼女の祖母が味噌をねかせる時はいつもユウナの木の下に置いていたそうだ。昭子さんの祖母は、そうすることで発酵が早いことを生活の中で知っていたのだ。藍も発酵によってできあがるので、おばあさんの知恵に習って試してみたところ、それが見事に的中した。あきらかに藍の発酵が早いのだという。また、「藍の花がさくのは、満月の時が多い」と昭子さんは語る。発酵と月の引力との関係があるのか科学的には分からない。昔の人は科学的な根拠は分からなくても、経験としてさまざまなことを知っていた。そうした知恵が伝統として伝えられてきたのだ。
「行き着くところはすべて昔の人がやっていた」
昭子さんが首都圏などで展覧会を開くと、人気があるのはなぜか八重山地方の伝統色だったという。藍、フクギの黄色、紅露の赤(茶)の3色だ。西表島は炭鉱の時代をさかいに「衣」の文化が絶滅してしまったので、何も無いところから自分で工夫して復元するしかなかった。復元された作品は、新しい創作的なものとよく言われたてきたが、実はそれは昔からみんながやってきたことだ。染織を追求していくうちにそれが分かってきた。
藍瓶の中の濃い緑がかった液体の中に布を入れ、それを瓶の外で広げると、見事な藍色にかわった。それは、まるで青い花が目の前でぱっとさいたようだった。同時に藍の独特な香りが鼻をついた。布といっしょに昭子さんの手首から先も青く染まっている。石垣島の市場で野菜を売っている老人たちが昭子さんの手を見ると、「あんたマイフナーね」と声をかけられるそうだ。マイフナーとは「働き者」という意味だ。
糸を紡ぎ、布を織り、染めるといった、この地方の女性たちがかつて当たり前に行い、生きてきた姿と、クリエーターとしての昭子さんの姿がかさなった。「行き着くところはすべて昔の人がやっていた」という昭子さんの言葉が少し理解できた。「伝統は創造の所産」そんな言葉が浮かんだ。

 左)石垣金星氏が、ソメモノイモ堀に連れて行ってくれた。ソメモノイモは伝統色「紅露」の原料。収穫はおもに冬場。イノシシのかじった物は質がいいといわれている。
左)石垣金星氏が、ソメモノイモ堀に連れて行ってくれた。ソメモノイモは伝統色「紅露」の原料。収穫はおもに冬場。イノシシのかじった物は質がいいといわれている。
右)メモノイモ(Dioscorea cirrhosa):ヤマノイモ科のつる性植物で、西表島と石垣島に分布する。


 左)淡い色に染めるときは、最初に瓶に入れる。何度か使っていくと、少しずつ弱ってきてしまうので、デンプンなどの栄養をあげながら様子を見る。
左)淡い色に染めるときは、最初に瓶に入れる。何度か使っていくと、少しずつ弱ってきてしまうので、デンプンなどの栄養をあげながら様子を見る。
中)淡い色に染まった布。薄い色はムラが出やすいので難しい。
右)染めをするときは、空気が澄んでいる朝をえらんでいる。
 藍染めの嫁入り点セット。
藍染めの嫁入り点セット。
上)ヒジリウチクイ。濃い色に染め上げた風呂敷で、道具を包んだり、かぶり物にする。ここに描かれている絣柄は意味があり、八つ玉には「矢」、九つ玉には「心(ククル)」が表現されている。嫁ぐ娘に対して、この家を出たら矢のように戻ってこないようにという親心が描かれている。濃く染め上げるというのも、思いの深さをあらわしている。
中)ミンサー帯。ミンサーは通い婚のあった時代に女性が男性にプレゼントしたものだ。その帯をモーアシビ(毛遊び)の時に男性が締めてくれれば、結婚が成立する。ミンサー帯は嫁ぎ先の家族の分だけを織っていく。
ミンサー帯に描かれた五つ玉と四つ玉の白い絣柄には「イチヌ ユーマデ」という「いつの世までも」という深い想いの意味が込められている。絣の両脇の白いラインには、お互いの真心を意味し、婚約の時の女性が男性に対する愛の証とされている。
下)ティサージ(手巾)。布はぐんぼう。婚姻する男性だけでなく、嫁ぎ先の家族全員に贈る。思いを込めてその人ができる技術や技を駆使して織られたもので、その思いが身につけてくれた人を災いから身を守るものと信じられている。親しい人の旅立ちなどにも、お守りとして渡されることもある。さまざまな色を使い、柄のくり返しもほとんどない。