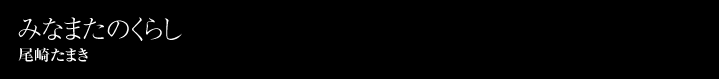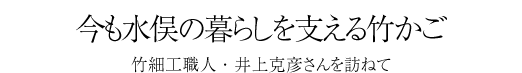![]()
2016.03.16
山の水俣
「水俣」というと海の印象が強いが、地図を見ると、山間部が海岸にせり出した平野の少ない山深い地域であることが分かる。この山あいに住む人々は、狭い土地を開墾し、石垣を積み上げ棚田を築き、そこで代々農作業をしながら土地を守ってきた。
竹細工職人・井上克彦さんが暮らす海抜約300メートルの久木野地区古里もそんな山あいの集落である。村のいちばん奥に棚田に抱かれるように、井上さんの住居兼作業場の古民家が建つ。太陽の光を受け、風にたなびく洗濯物が気持ちよさそう。子どもがぴょんぴょん跳ねている。その背後で見守る井上さんと奥さん。水俣に移り住んで17年、すっかりこの地は井上さんの生きる場所となった。
竹の声をききながら
「今日は、背負いかごの底の部分を編もうと思います。その前に竹を洗いに下の川に行きます」
あまたある真竹のなかから一本選ぶと、ひょいと抱えて、家の裏を流れる川まで降りていく。
竹には表情があって、背負いかごになりたがっている竹、ざるになりたがっている竹があり、そんな竹の表情をよみ、竹を選ぶのが竹細工職人の仕事。尊敬する竹細工職人の大先輩、故廣島一夫さんも言っていた。「いつも竹のなりたい形を考えている。俺の気持ちで……じゃいかん。竹の気持ちでやらんと」と。「自分はまだまだ。いつも試行錯誤で余裕がなくて」と冷たい水で竹を磨きながら井上さんは言う。
竹は10月11月の、下弦の月から新月に向かう時期に一年分を山から切り出す。これこそどんな竹細工になりたがっているか竹の声に耳を傾ける最初の作業。しかし井上さんは「竹の声をききたいと思うものの、いまだ難しい」という。日々修業を重ね、誰よりもストイックに竹細工に対峙する井上さんの口からこの言葉をきくと、竹と向き合うことの深さと果てしなさ、職人の仕事に終わりがないことを感じずにはいられない。
竹を洗い終えた井上さんは、作業場へ。定位置に座るとやおら道具を取りだし、竹を繊維に沿って割きはじめる。魅入ってしまうほど滑らかで美しい手さばき。直径15センチはあろうかという真竹が、最終的には厚紙ほどの薄さに割かれていく。これをもとに竹細工を編んでいく。ただ無心に素早く割いているように見えるが、「指の感触に集中して、竹の節や繊維を見ながら、この竹はどんな形になりたがっているのか、このひと筋はどこに使うべきか見極めながら作業しています」。井上さんと竹との静かな対話の時間が流れる。
「次の作業に入ると一気にやってしまわなければならないので、ここでちょっと休憩。 おしめを干してきますね」
3年間師匠のもとで修行をし、その後独立。約10年ほど一人暮らしをしていたが、気づけば四人家族に。独身のころは、深夜まで竹仕事をしていた井上さんも、「家族ができてからは、夕方を境に、竹の仕事はお終いにして、家の仕事をするようにしています」という。作業場を後にした井上さんは、一気にお父さんの顔になる。
竹かご文化が残る水俣
生まれも育ちも都会っ子の井上さん。大学卒業後、商社に就職したが「何か違う」と退職。その後、インドでNGOのボランティアに従事、帰国してJICAに就職するも、違和感がぬぐえない。一般的に見るとエリートコースだが、当の井上さんは仕事が続かない自分に苛立ち、将来への不安におののき、「いったい自分は何をしたいのか」と悩み苦しむ日々だったという。そのなかで、「ものづくりがしたい」という自分の内なる声に気づき、同時に竹かごと出会い、魅入られ、竹細工職人の世界に飛び込んだ。
「これだ」というものに出会ってからは迷いはなかった。修行する場を探して全国行脚。師匠となる渕上泰弘さんと出会い、関東から水俣に移住、弟子入りを果たした。1999年、井上さん30歳の冬であった。
水俣といえば、日本のみならず世界中から移住者がやって来る。「多くは水俣病問題で集まった人たちです。しかし私は、工芸品ではなく生活道具として使われる竹細工を追い求めていたら、この地に行きついた。それだけなのです」。プラスチック製品が竹かごにとって代わり、竹職人が消えて行く時代においても、ここ水俣では、漁や農作業、台所仕事で竹かごが使われ、職人もそれで生活できるという昔ながらの生活様式がまだ残っていたのだ。
「竹細工のおかげでここの住民になれた気がする」
集落を歩いていると、庭先で竹ざるいっぱいの野菜を洗う女性がいた。そこには大根、白菜、小豆などが大小さまざまなざるに干され、並んでいる。聞けば、今使っているざるは井上さんの師匠が作ったもので、彼女のお母さんの時代から使っているのだとか。「これ(竹ざる)がなかったら、なーんも(家仕事が)終わらんとですよ」と言う。井上さんも「これは師匠のかご、こちらは私のですね。それからこれは師匠のざるを私が修理したものです。こんなふうに修理しながら今も竹かごを使っている人がいるから、自分の生活が成り立っているんです」
またある家では、ありとあらゆる形のざるが納屋に掛けられていた。「お米を洗うのも、野菜を置いておくのも、天日干しするのも全部竹かごです」と92歳のおばあちゃん。「井上さんのかごは、井上さんの性格どおり、きめ細やかでしっかりしていて、使いやすいですよ」。独立して最初に大量注文をしてくれたのもこのおばあちゃんだった。「ありがたかったです。その気持ちに報いるために一生懸命つくりました」。これを機会に地元の人からの発注も増えていった。発注があるごとに、その人が使いやすい竹細工にするために話しをし、会話のたびにお互いの距離が縮まっていった。そうしてつくったごからは信頼も生まれた。そして気づけば、集落の一員として受け入れられ、頼りにされるようになっていた。「竹細工のおかげでここの住人になれた気がします」「そんな竹細工も使っている多くは、大正から昭和ひと桁の高齢者。この世代の人がいなくなっても、竹かごのある生活文化や知恵が絶えないよう、その人、その家の生活に則した竹かごをこれからもつくっていきたいです」
竹かごは生きている
山から切り出したままの生の真竹で編まれたかごは、出来上がった当初は青々としている。人に使われるうちにやがて黄色になり、数年すると深い橙色に、そしてやがては艶やかな飴色に変わっていく。ときに飴色のかごに青い目が混じっているのを目にするが、それは修繕をした跡であり、長らく大切に使われている証でもある。
「以前、100年以上も前に編まれたかごの修理を頼まれたことがありました。古いかごを編みほどいていくとき、手に取るように、それを編んだ職人の気持ちが感じられました」「修理しながら普通に使えば何世代か使えます。道具は手入れをしながら使うほどに、風格と味わいを増していくものです」。新たな命を吹き込まれたかごは、これからもうひと頑張りもふた頑張りもしてくれるだろう。
竹かごはまさに「生きている」。しかし、生きているからこそ、修理をしながら使ってもいつしか役目を終えるときがやってくる。「私はそれがお終いなのではなく、自然に還っていくのだと思っています」。竹かごになりたかった竹は、熟練の竹職人に見いだされ、竹細工となり、最後は自然に還る。そして次なる命へとつながっていく。どこにいても違和感があった井上さんが見つけた自分らしく生きる場所は、自身が大切にしたいものを受け取り、受け継ぎ、手渡していく、そんな営みがある場だったのかもしれない。