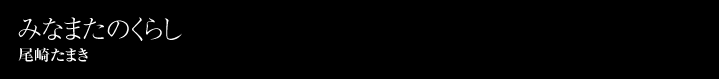![]()
2016.10.26
水俣で甘夏を栽培し、マーマレードを作る仕事
一年の集大成ともいうべき収穫時期のみかん山に、「ガイアみなまた」の職員で面白い青年がいるときいて訪ねたのは2016年2月初旬。南九州の元気な太陽を跳ね返すように光る深緑色の葉。その下でたわわに実る橙色の甘夏。背伸びして木々越しに先を見やれば水俣の海がきらめいている。そんなみかん山で、額に汗を光らせた青年がひょいと頭を下げて、さわやかに言い放った。「こんにちは、高倉草児です。水俣で甘夏の産直をし、マーマレードを作りながら生活しています」。
繁忙極まるこの時期、彼はそう言うと再び作業に戻った。手入れがしやすいように低木に栽培されたみかんの木の下を、腰をかがめながら右に左に飛び回っている。高倉草児さんの妹・鼓子(つづみこ)さんやシルバー人材のみなさんがもいで、コンテナに集めた甘夏をひとりでモノレールまで運び、載せ、そのモノレールからトラックに積み上げていく作業をもくもくと続けている。甘夏の入ったコンテナは1個約20キロ、それを70個トラックに積む。腰や手首に負担をかけないよう、また効率よく運べるよう自ら編みだした「オランウータン歩き」でコンテナを運び、積み上げる。トラックがいっぱいになると、次は倉庫に運ぶ。倉庫では、ガイアのメンバーが待機しており、みなで荷をおろし、再び倉庫に積み上げる。出荷までしばらく寝かせるのである。もぎたての甘夏はしばし時間を置くことで、酸味が抜け味がまろやかになるのである。この作業を1日2回繰り返す。
「シルバーさんたちは元農家でプロ、ベテランばかり。そのなか、僕は、最初の頃は体じゅうテーピングだらけ。いろんな意味で満身創痍でした」。それもいまや入社7年目。周囲に指示を出しながら、力仕事を一手に引き受ける。「この仕事で体も人生も鍛えられました。まさに生活が精神と身体を作るんですね」と草児さん。
はてしなく続くかと思われた作業も、「休憩時間ですよー」の声でひと休み。みなで木の下に集まり、お茶やお菓子をいただく。重労働のなか、憩いのひととき。老若男女、おしゃべりに花が咲く。
「草児くん、昔はすごい頭(髪型)やったもんね」
「ああ、ひどかったねー」
「それがもうじきお父さんになるとだけんねー」
入社以来の顔見知りであるシルバーさんたちのひやかしに、草児さんの表情もゆるむ。「ガイアみなまた」の職員として一連の作業を任された責任者の顔から、いち青年の顔に戻る。
水俣病問題支援活動の渦中で育った少年時代
草児さんは、水俣で生まれ、高校を卒業するまで水俣で過ごした。大学は神戸へ。卒業後、日本生協連合会に就職し、東京に移り住む。その後、水俣にUターンして、父親らが創設した「ガイアみなまた」に入社。現在、次世代を担う若き大黒柱として働いている。
両親を含め現在ガイアで働く仲間は、1970年代の半ば以降、水俣病問題をきっかけに関東をはじめ各地から水俣に移り住み、社会運動を支えてきた支援者たちだ。彼らは運動と支援に取り組むなか、声高に叫ぶだけでなく、視点の置きどころとして、まずは自分たちの生活の仕方を考えることで水俣病を引き起こした社会構造を問い直そう、また思想を実生活で体現することこそが大切だと考えた。
そこで、被害者家族、支援仲間とともに、「被害者が加害者にならない」と誓い、1977年に減農薬の甘夏を栽培する「患者家庭果樹同志会」(のちの生産者グループ「きばる」)を立ち上げた。そして産直という販路の道を開き、のちには甘夏をマーマレードに加工して販売することで生計を立てる生き方を選んだ。
そんな両親のもとに生まれたのが草児さんである。幼い頃から職場には「人見知りになる暇がない」ほど次々と旅人や学生が出入りし、人であふれていた。食事も仲間の家族全員で、職場に集まって食べる。つねに議論があり、キレのある会話が飛び交う賑やかな食卓だった。炊事は当番制で「これが当たり前だと思っていた」と草児さん。いまも当番制、みなで集まって食べるという基本は変わっていない。
父・史朗さんは水俣病患者団体「チッソ水俣病患者連盟」の事務局長でもあり、まさに水俣病問題支援活動の渦中で育った草児さんだが、子どもの頃、水俣病についてことさら深く考えることはなかったという。地域のおとなたちのなかにある対立も、社会の歪みも感じなかった。それより友達と遊ぶことに夢中だった。
水俣病を語れない水俣生まれの水俣育ち
大学に通うようになってからのこと。「水俣出身だったら水俣病のことを教えてくれないか」と友人に言われた。草児さんは何も答えられなかった。水俣病について何ひとつ知らないも同然だった。これはもしかして恥ずかしいことじゃないか?――それから帰省のたびに知り合いに話を聞き、大学では図書館に入り浸った。そこには水俣病関連の本がたくさんあり、自分たち家族のことも本に載っていた。そのとき初めて親たちがやってきたことの意味を知った。そして「その中で育った自分」の役割についても考えるようになった。この入り組んだ歴史のなかで親世代がやってきたことを受け取り、今後50年、100年と語り継ぐことは、自分を含めた未来を生きる人々の生活にとって何かしらのヒントになるのではないか、そして、それが自分の役割かもしれないと漠然と感じた。しかし同時に、「当事者の実感」として水俣病を語れない自分たちの世代は、親たちと同じことはできない。だからこそ、自分たちには自分たちの語り方、生き方があるはずだと考えはじめたという。
父や先輩たちが築いてきた支援者と生産者、そして消費者の関係性を受け継ぎ、発展させたい
「父や先輩たちが水俣病被害者支援と自身の生活のために続けてきた甘夏の生産販売、その事務局として1990年に設立した『ガイアみなまた』。これらが生業としてここまで持続できたのはある意味奇跡だ。その奇跡は、プライドをもって甘夏を作り売って生きてきた被害者の皆さん、支援者、そして消費者が、信頼で結ばれていたからこそだと思う。親たちは一代で終えるつもりだったかもしれないけど、僕が帰ってきてしまったからには、それに、甘夏園があり生産者がいて、それを買ってくれる人がいるからには、とりあえず自分が受け継いでその関係性を『続ける』という道を選ぶべきじゃないかと思ったんです」。学生時代から考え続けてきた自分の役割と一生の仕事がひとつに重なった草児さんは、故郷水俣に帰る決心をする。
水俣に戻ってくると、自然発生的に「水俣でもっと元気に楽しく暮らそう」と思いを同じにするパワフルな若者が集まってきた。水俣の食、自然、暮らし、文化を再発見し、自らもそれを楽しみながら、外にも情報を発信していこうと「あばぁこんね」というグループが生まれた。マルシェを開いたり、遊休地を耕して米や野菜を作ったり、水俣の海水から塩を作ったり。やりたいと思ったことをかたっぱしからやった。草児さんも精力的に水俣を掘り起こし、遊び、人とつながっていった。
水俣病の公式認定から60年。若い世代にできること。
しかし水俣に戻ってからというもの、「何かをやった気になっているだけかもしれない。もう一度自分の足元、自分の仕事を見つめ直さなければ」という焦りにも似た気持ちに襲われていた。「あばぁこんね」の仲間たちも、期せずして同じような過渡期にいたようだった。親たちが命がけで築いたものを自分たちはどうしていきたいのか?――それぞれがそういう視点で個々の仕事や役割を見つめ始めた。「自分の場合、それは『一対一の関係性づくり』。生産者との関係はもちろん、この甘夏を、マーマレードを買ってくれるお客様とも個々に信頼関係を築き、それを守り続けること。そのためには、つねに真面目に正直に、身の丈で、いっぱいいっぱい仕事をすることが大切だと思っています」と言う。また、「水俣で言われる『もやい直し』のように、大きな枠組みで見る視点と、狭い範囲を着実に固めていく視点の両方が必要なのだろうと思います。大きな枠組みで見るというのは僕は正直いって苦手なのですが、いずれ身につけていく必要がある。ただ今は、自分の半径1mの範囲から一対一の関係性を積み上げ、固めていくことに全力を傾けたい。それは苦悩や煩悶を含めた、言葉に言い表せない生活そのもの、生き方そのものです」と。
今年、妹の鼓子さんがガイアの仲間に加わり、強力なマンパワーとなった。そして草児さんは父となり、夫から親という新たな責任が加わった。「甘夏」「マーマレード」「産直」にも、新しい可能性と新しい時代の価値を添えてスタートを切りなおす時が来た。
水俣病公式認定から60年。「自分たちにできることは何か」と悩み続ける若い世代が、水俣を引き受け、さらに若い世代に伝えようとしている。親から受け継いだ、生活者たれという生き方、うそのない生き様を礎にして、変わらぬものを伝えるために新たな試みを続ける、そんな時代がやってきた。
ガイアみなまた
http://gaiaminamata.net