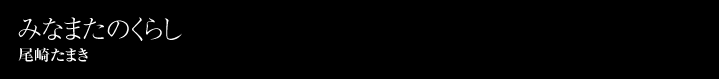![]()
2016.12.21
完全無農薬・無化学肥料のお茶栽培
水俣市街から車で山手へ30分。標高580mの石飛(いしとび)高原に、「天の製茶園」の天野さん一家が住む自宅、工場、そして茶畑がある。「天の製茶園」は、一家の父・茂さん、そして代表の長男・浩さん、次男の礼さんで完全無農薬・無化学肥料のお茶を栽培・販売しているお茶農家、そして老舗「とらや」の紅茶羊羹にも使われている知る人ぞ知る国産紅茶「天の紅茶」の製造元である。
四季を通じて、また一日のうちでも寒暖の差が激しく、さらに霧深いこの地は茶づくりに適した地として昭和初期に開墾されたが、戦争で荒れ果ててしまった。戦後、開拓団が入植し、苦労のかいあってその荒地も再生され、後継者もでき、石飛地区は茶畑が広がる一帯となった。
水俣病で苦しんだこの地で農薬を使ったものをつくりたくない
茂さんが入植した父親の後を継ぎお茶農家となったのが1971年18歳のときだった。少しずつ無農薬栽培を試しながら、1979年から完全無農薬・無化学肥料栽培の道を歩きはじめた。「自分でつくって、自分で売るところまでやりたかった。そのためには特徴がなかといかん」と考え無農薬栽培を始めたという。さらにその根底には、水俣病で苦しんだこの地で農薬を使ったものをつくりたくない、生産者の責任として自分の家族やお客さんが口にするものに農薬は使いたくない、という強い思いがあった。
しかしその道も平たんではなかった。化学肥料を使わないため収量は減り、また、農薬を撒かないため草がぐんぐん成長し、来る日も来る日も果てしない草取り作業が続いた。「農薬ば撒かんでよかけんラクかと思ったら、草取りがいちばんの重労働だった」と茂さん。さらに、今でこそ無農薬や有機栽培はその手間や価値が認知され価格に反映されているが、当時は見た目が美しい慣行栽培のお茶のほうが高く買い取られていた。精魂込めて茶葉をつくっても安い値でしか取り引きされず、「それじゃ、生活できんけんね」と先々のことを考えるとこのままではいられないのが現実だった。そんな切実な理由に加え、「人と同じことをしたくない」「おもしろいことをしたい」そして「確かなものづくりをしたい」という茂さんの思いが「天の紅茶」誕生へとつながっていくのだった。
「素人の強み」で生まれた国産紅茶
石飛地区は高冷地であることに加え、お茶づくりに適した赤土の火山灰土を擁した、まさに良質なお茶が育つ地である。しかし高冷地であるがゆえに、一番茶の茶摘みができるのが、いわゆる八十八夜(5月2日前後)を過ぎた5月中旬。そのころはすでに新茶が高く売れる時期から外れてしまい、どんなに良いお茶でも安値の取り引きとなってしまう。さらにペットボトルのお茶の消費量は増えたが、自分で日本茶を入れて飲むという当たり前の風景が少しずつ失われつつあった。すなわち茶葉の消費量が大幅に減り、「このまま普通に緑茶だけをつくっていても生活は成り立たない」という時代がそこまで来ていたのだ。
「人間、行き詰るといろいろ考えるたいね」。そんなとき茂さんのアンテナに引っかかったのが「緑茶と同じ茶葉からつくる紅茶」だった。さっそく自分で本を見ながら研究したり、静岡で番茶から紅茶をつくっている生産者に会いに行ったりし、「売る先もなかとに紅茶ばつくりはじめたとよ」と茂さん。「紅茶は素人だけん、枠を超えてなんでもできた。素人の強みたいね。失敗もひらめきに変えられた」と。いまから約25年ほど前のことである。
紅茶の専門家からみると、緑茶の品種からつくられる紅茶は、紅茶らしからぬものだったかもしれない。しかし茂さんは「国産紅茶のよさがあるけん、それでよかち思って。火入れも発酵も、ひとひねりもふたひねりもして美味しと思える味にしあげていったったいね」と。それは渋みが少なくほんのり甘く、華やかでいて柔らかい味。全国でも珍しい無農薬栽培の紅茶が出来上がった。
地元水俣で安心安全、「美味しい」をつくり届ける誇らしい仕事
長男の浩さん(三代目)が家業に加わると、さらに紅茶づくりに力を入れた。同時に浩さんはマーケティングや販路開拓にも力を注ぎ、「天の紅茶」を知ってもらうために動いた。イベントに参加したり、講演会に行ったり呼ばれたり。そのうち仲間が増え、ネットワークも広がり、天野さん一家がつくる紅茶も少しずつ知られるようになった。1996年に開催された「東京水俣展」で「天の紅茶」が話題となると、デパートで扱ってくれるなど販路も広がり、固定ファンも増えた。そうするとこれまで以上に「美味しい」「ここの紅茶なら飲める」の声が直接届くようになり、「天の紅茶」の広がりを実感できるようになった。地元水俣で美味しくかつ安心安全なものをつくり届けるこの仕事が誇らしかった。
現在では三代目として「天の製茶園」を継ぎ、お茶の味を守り、さらなる味の追究をする浩さん。新茶や紅茶の時期は、朝から晩まで加工につきっきりでカンヅメになる。葉の状態や気候にあわせて、蒸す時間や温度、紅茶だったら発酵を調整する。加工途中の茶葉でお茶を入れ、味や色を何度も確かめる。浩さんはそれを観察というより一瞥するだけだが、その一瞬は真剣で、声をかけるのがためらわれるほどの集中力である。加工が終わり、機械を洗い、床の掃き掃除をするとすでに深夜である。工場を出ると、最近ではめったに体験できないほどの真っ暗闇。その上では万の星が輝いていた。
帰宅後は出荷する茶葉の袋詰め、シール貼り、箱詰めして発送準備と作業が続く。それでも浩さんの話題はお茶のこと。「一番茶の新茶は緑茶に、二番茶は紅茶、番茶や緑茶の在庫はほうじ茶にしています。父と長年やってきて、やっとお茶の全部を捨てるとこなく活かせるようになりました」。「うちで育てている茶葉は、半分以上が在来種。先代たちが京都などから種を取りよせ、直播し、発根させて育ててきたものです。なかには樹齢90年くらいのものもありますよ。根がしっかり深く張り、病害虫にも強い無農薬栽培向けの品種。今後もこの在来種に力を入れ、野趣あふれる風土の味を出していきたい」と楽しそう。そして目の前の茶農家を一生懸命やることで、自分らの子どもの世代、その次の世代と、100年200年続けられる農業やモノづくりにつなげたいと力強く語った。
あの水俣の子どもたちが光ある明日、受け継がれる未来を考えるおとなに育った。
茶葉の緑、空の青だけの世界のなか、遠くにぽつんと赤い茶摘み機。近寄ると摘みとったばかりの若い茶葉の香りが漂ってくる。そこでは次男の礼さんが茶摘み機を器用に操りながら一番茶を摘んでいるところだった。茂さん、浩さんがこだわりのお茶マイスターであるなら、礼さんは茶畑の現場を取り仕切る実働部隊のリーダーである。海外からの研修生や入れ代わり立ち代わり訪れる農業体験者たちと一緒に茶摘みを段取り、自ら率先して動く。礼さんのおおらかな笑顔にみなもリラックスして仕事に励んでいる。
礼さんが摘みとった茶葉を浩さんが受けとり加工しているあいだ、茂さんは紅茶専用の小屋を建てたり、ほうじ茶を焙煎したりしている。とりたててミーティングをしている様子もないが、段取りもスムーズで、どこで誰が何をしているのか把握しあっているのが不思議である。鮮やかな親子のチームワークである。
以前茂さんが「生産者はモノづくりが仕事。現場にどっぷりつかって、汗まみれ泥まみれになって、茶と語りあわんと喜びはなか。そげん若者ば見つけて育てんと農業の将来は厳しか。それを伝えるのも私らの仕事たいね」と言っていたが、まさに、ここにふたり、その楽しさも辛さも、またそれ以上の喜びがあることも知っている若者がいるではないか。生産者として生まれ育った地元に根を張り、誇りをもって暮らしているふたりが。
悶え苦しむような時間を刻んだ水俣だが、子どもたちは光ある明日、続いていく未来を考えるおとなに育った。それはこの地に暮らし、人と人、人と自然のつながりを再起させてきたおとなたちの生き様、精一杯今日を生きてきたおとなたちの姿そのものだろう。