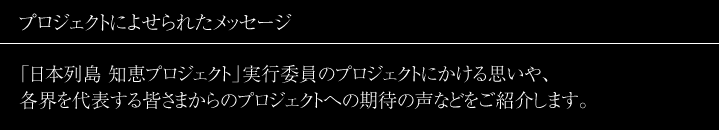暮らしの海の知恵
吉村喜彦
作家
初めて沖縄に行ったとき、サンゴ礁で海の色がくっきりと分かれているのに驚いた。
リーフの内側は輝くばかりのエメラルドグリーン。外側はインク瓶からこぼれたようなマリンブルーだった。
サンゴ礁の内側の浅い海はイノーといわれ、島人たちがシャコ貝やサザエ、アーサなどを採りに出かける「暮らしの海」だ。
サンゴ礁の外は「ふかうみ」と呼ばれ、男たちがサバニを駆ってカツオやマグロなどの回遊魚を追う。普段の暮らしと離れた、死と隣り合わせの海である。沖縄では日常の海と非日常の海が、色ではっきり区別されている。
サンゴ礁がないからわかりにくいが、内地の海にもそうした二つの海があった。
ぼくが大阪湾の近くで育った昭和30年代は、毎朝海でアサリを採ってきて、味噌汁の具にしていた。あの大阪にも暮らしの海があったのだ。が、やがてその海も埋められ、今はコンビナートが林立している。
イノーに代表される「暮らしの海」はいわば海の縁側である。
かつて家には縁側があった。祖母と一緒に日向ぼっこをし、通りがかった人とお茶を飲みながらお喋りをした。内と外とのあわいにある縁側は、暮らしにゆとりや間を与えた。しかし、いま陸でも海でもそのやわらかな場所は急速に姿を消しつつある。
魚も減っている。いつまで魚を食べていけるかわからない時代だ。埋め立てや生活排水で藻場や干潟がなくなり、海の環境が悪化している。しかも、最新技術の漁探やGPSを備えた船で魚を獲りすぎている。いまや暮らしの海はもとより、遠海の魚すら獲り尽くされようとしている。
漁業は沿岸(暮らしの海)から始まった。人々は海を畏敬し、魚貝や藻を獲りすぎず、海からの恵みをいただくという謙虚な気持をもっていた。静かな知恵を使って、トゥーマッチ(too much)とは無縁の暮らしをたててきた。バランスや足ることを知っていた。
この時代を生きるぼくらのたましいは、どこか病んでいる。その疲弊や衰弱から恢復するには、暮らしの海に今も生きる人たちの知恵に学ぶのが一番ではないか──ぼくらの生のパラダイムを変えるツボ(経絡)を、見つけられるかもしれない。
そのツボを探り、自分自身が変わるために、浜をめぐる旅に出ようと思った。