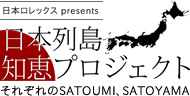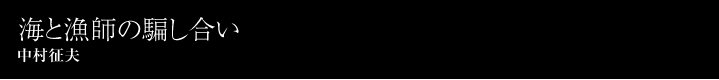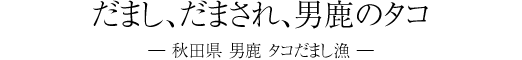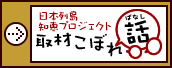![]()
2009.12.07
なまはげの里、男鹿
秋田県男鹿半島。
ゆるやかに弧を描く海岸線から忽然と突き出た半島は、かつて島だった。川から運ばれた土砂が堆積して、島は陸と結ばれ、半島となった。
その成り立ちは函館山や潮岬などと同じで、地図で見ると、男鹿半島は海に向かって振り上げられた斧のような恰好をしている。
男鹿は、また、「なまはげ」でも有名だ。
大晦日の夜に、怖い鬼の面をつけた男たちが、大きな出刃包丁をもって家々を訪れて、「泣ぐ子はいねがーっ」と大声でわめきながら、怠け者や子ども、初嫁を探して暴れ回る。
ぼくも子どもの頃、その「なまはげ」の姿を雑誌の写真で見て、あまりにも怖くて、ページをめくることすらできなかった。
男鹿といえば、ぼくにとっては「なまはげ」の居住地なのである。
そんな半島の一角で、「タコだまし漁法」があると訊き、一路、取材に向かった。
低気圧が来ていた。
秋田空港に降り立つと、風が強く、雨脚も白く煙っている。
が、不思議なことに、一時(いっとき)、猛烈な雨が降ると、しばらくして小止みになり、薄日が射して虹まで出る。それが幾度も繰り返される。
まるで南の島でスコールに遭ったようだ。
地球温暖化というけれど、温暖化という命名は甘い。熱帯化といった方が適切なのではないか。このままいけば北極の氷は2030年には消えてなくなるとも言われている──。
そんなことを考えながら車に揺られていく。
八郎潟をかすめ空港から一時間半ほどで男鹿半島・門前(もんぜん)集落に着いた。
前浜は小さな漁港になっていて、南西方向に開かれた湾。一部に堤防があるが、そこ以外はテトラポッドが並べられている。
堤防とテトラの向こうから大波が白い牙を剥いて襲いかかっている。波の高さは4メートル以上だ。
鈍色(にびいろ)の空が低く垂れこめ、ときおり雲の切れ目から幾条(いくすじ)もの光が海に差し込む。
文字通り、タコをだまして獲る「タコだまし漁」
タコだまし漁をする秋山秀美さん(56歳)は、民宿を営み、お客さんへのおかずを獲るために漁に出る。
潮のしぶきのかかる浜を一緒に歩きながら、秋山さんは渋い顔をして首を振る。
「この波じゃあ、出られんね」
いつもどのあたりでタコを獲るんですか?
「テトラの前。岩がボンボンある所。実はあそこはテトラ作るために岩こわして一つにまとめた所なの。昔はもっと大きな岩がドンとあった。 前に台風来たときに『何とか船が流されんようにしてけれ』て集落で陳情して、テトラが入った。
んだども、テトラ出来てから、タコ少なくなったな。
今年はほんと不漁だ。形も小さい。水温も高い。素潜りやってると、岩のとこさのガゴ(穴)ん中にタコは必ず入ってるのが見えるんだ。ん だども、今年はあんまりいねがったもの」
タコはどうやって獲るんですか?
「深くても1メートル、だいたい膝くらいの海に入って、胴長はいて獲るんだよ。左手に竹竿もって、その先にガニ(蟹)の形の疑似餌や『だまし』をつけて、海さ入ったら震わすんだ。ガニッコ(蟹)だあって感じで。へば、タコがガニと間違えて、それに抱きついてくる。そこをすかさず、右手に持った竿でキュッと引っ掛ける。先にイカ釣りの鉤(はり)つけてるからね」
タコをだまして獲るので、「タコだまし漁」というそうだ。
市販の疑似餌、手作りの「だまし」
「子どもの頃は遊びだった。『タコ、だましに行ってくるだー』って、仲間とよく行ったもんだ。昔は疑似餌なんかないから、自分で『だまし』を作ってた」
疑似餌と「だまし」は違うんですか?
「疑似餌は釣具屋で売ってる既製品。『だまし』は自分で作る。
普通の『タコだまし』は赤い布(きれ)こ付けたり、ホオズキ付けたり。赤い布こはまるめてイボみたいにして結わえつけるだけ。祖父ちゃんが蟹の形にしてたから、それを真似した。タコがいっぺいたから、そんな『だまし』でもその頃は獲れたんでねえの?
最近は疑似餌ばっかしだ。『だまし』よりよく獲れる。疑似餌は匂いも良いんでねえかな。タコの好きな匂いがするんだべ。つるつるして光るのも関係あるべし。ガニも甲羅が光るし。タコだって馬鹿でねえから、わかるんだ。
『あんまり獲れすぎるんで、もう売るの、禁止になったべ』って釣具屋の若社長が言ってた。タコなくなってしまうからな。これからは、また 赤い布に戻るんでないか。したば、また、タコさ増えると思うけどな。
まあ、海の状況も変わってきてるし。
昔はこの辺でサワラなんか獲れなかった。んだども、今は大漁だべ。こんなのも、いっぺ流れてくるし」
小石だらけの浜を秋山さんが指さすと、ブヨブヨのゼリー状のものが散乱している。
「エチゼンクラゲだ。もう津軽海峡まわって三陸まで行ってるらしいべ」
誰にでもできる、浅瀬のおかず漁
夜は雷鳴が響き、堤防にあたる波がドーンドーンと轟いて、なかなか眠れなかった。
翌日はよく晴れたが、南西の風が強く、門前集落にまともにぶつかってきていた。テトラにぶつかる波は5メートルを超えている。たくさん の波の花がふわふわと浜に打ち寄せられ、潮つぶてで眼鏡は真っ白になる。
たぶんタコは無理だと思ったけれど、秋山さんに一応漁をやってもらいつつ、話をうかがった。
「『だまし』は浅い所でやるから、男も女も、子どもだってできんだべ。
川さ行けば、10センチくらいのカワガニ必ずいたもんな。海の岩場さ行けば、アブラガニって2センチくらいの小っちゃいガニッコ(蟹)いっぱい遊んでるんだもの。
そんなガニッコ、竹竿の先につけたりして『だまし』やったね。
どこさ行ってもタコはいたし、家のおかずくらいなら、すぐ獲れた。家に帰ると、大根と芋と醤油入れて、ざく切りにしたタコを炊いて食べ たもんだべ」
獲り方は誰に教わったんですか?
「先輩方が教えてくれるんだ。小学校入ったら、もうタコさ獲ってた。『まんず、ガニッコ獲ってくるべ』。捕まえてくると『よし。タコだまかしに行くぞ』」て。昭和30年代半ばの話だ。
コツはタコのガゴ(穴)を覚えておくこと
竿は山の竹で作る。力を入れなくても、よく撓(しな)るから、だましにゃ、もってこいだ」
季節はいつが良いんですか?
「9月から10月末くらいまで。秋になるとタコは浅瀬にやってくる。夏は深い所にいるんでねえかな」
タコを獲るコツって何ですか?
「んだな…まんずタコは岩と岩の隙間に、だいたい一匹でいる。そのガゴ(穴)を覚えておくのは大切だな。
んだども、台風やら低気圧やらやってきたら、海の中がまるで変わる もんね。外から見たらわかんねだども、中はものすごく変わってる。そうするとタコの住処(すみか)も変わる。また、最初からガゴの場所を探さねば。
あとは…んだな…タコが抱きついたと思ったら、その瞬間、スッと鉤で引っ掛けること。タコは疑似餌や『だまし』を抱えて穴ん中に引っ張ってくからな。自分の家で餌を食べる習性があるんだ。一度、中さ入ると、タコを引っ掛けようと思っても、なかなかできねえもの。
タコはグググーッて引っ張ってくんだ。そうして穴ん中から脚一本ぴろーって出してきたり。脚だけ出して、頭は絶対出さねえから。
網で獲られるときも、必ず頭隠すんだ。タコは、頭、急所なんだべなあ」
ちぎれ雲が青空を飛ぶように流れていく。
タコは岩の隙間で「やれやれ。今日は低気圧のお陰で助かったよ」と 一服しているのだろうか。今日も、一瞬たりとも、その姿を見ることは できなかった。
タコの呼びかけを伝えた低気圧の海
タコにまつわるこんな民話がある──。
昔々、婆さんが海辺で洗濯をしていた。
すると、目の前に大ダコがあらわれて、すぐ切れと言わぬばかりに一本の大脚を差し出した。婆さんは早速その脚を切り取って帰り、喜んで食べた。翌日もまた洗い物をしていると昨日のタコがやってきて脚を一本切り取らせた。
こうしたことが7日間続き、やがて8日目。婆さんは「今日こそは頭も一緒に獲ってやろう」と思って海辺に出かけていった。タコはいつも通り、残りの一本脚をにゅるりと出して待っていた。
そうして婆さんがその脚を切り取ろうとする。
と、急にタコは躍りかかって、残りの一本脚を婆さんの首に巻きつけ、海の底にグイグイと引っ張っていった。
タコが獲れなくて、よかったのかもしれない──。
疑似餌で獲りすぎるなと、きっとタコが海底から呼びかけているのだ。「元の『だまし』で十分でねえか?欲かくでねぇ。あんたとおれとのバランスってもんがあるだろ」
あるいは昨夜の風と波、いや、サワラが獲れエチゼンクラゲが押し寄せる海は、ぼくらに怖れというものを知らしめる「なまはげ」だったのかもしれない。
自分たちの勝手な計画通り世界(ものごと)は進まないのだ。
そんなこんなを考えられたのも、すべて低気圧のお陰である。
タコに呼ばれて男鹿に来たけれど、タコに上手に騙されたのかもしれない。