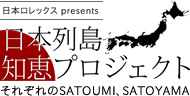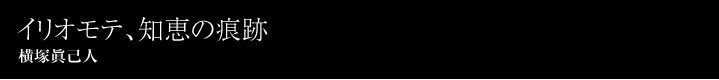![]()
2016.07.15
沖縄最古民家の10年に一度の茅葺き屋根の葺き替え
築年数がおよそ150年と推定される沖縄県最古の民家が、西表島の祖納集落にある。新盛家だ。1994年に沖縄県の有形文化財の指定を受けた頃は人が住んでいたのだが、現在はこの家で生活する人は誰もいない。有形文化財といえども、村人たちにとって展示物ではなく、つい最近まで人が住んでいたご近所の民家であるという意識が強い。この先、誰かが住むかもしれないという思いは消えないのであろう。
新盛家は釘や金具などを使わずに楔を使った、貫木屋(ヌキジャー)と呼ばれる建築様式で、その材料はイヌマキ、センダン、イスノキ、オヒルギ、シマミサオノキ、トウズルモドキ、コミノクロツグ、チガヤなど、すべて村の近くでとれる植物ばかりが使われている。150年以上も前からこの土地の自然とともに生活をしてきた村人の知恵と技術の結晶が、この家作りにも注がれている。幸運なことに10年に一度の茅葺き屋根の葺き替え作業が始まる年にあたり、私はその材料集めから参加することができた。
マングローブの一種、オヒルギを海水沈め、丈夫な垂木にする
 オヒルギ (Bruguiera gymnorrhiza):
オヒルギ (Bruguiera gymnorrhiza):
ヒルギ科。マングローブ樹種のひとつ。マングローブとは植物そのものの名前ではなく、真水と海水の混ざり合う汽水域に生育する植物の総称。世界にはマングローブ植物は100種類ほど知られているが、日本では7種類が見られ、そのすべてが西表島に生育している。
まずは、どの材料よりも先に集めておく必要があったのは、垂木に使うオヒルギだった。それは、切った材を2〜3ヶ月の間、海に沈めておくことが必要で、そうすることで材がより堅くなり虫もつきにくくなるのだという。オヒルギは海の潮の影響をもろに受ける汽水域に生えるマングローブ植物なので、塩水に対して耐性があるのだろう。
そういえば、私が西表島に住んでいた頃、地元の人から雌の鶏をいただいたことがあって、その鶏小屋をどのように作ろうか悩んでいたときに、地元の人がそれならいい材があるといって、とってきてくれたのがオヒルギだった。マングローブ植物は勝手に切ってはいけないので、びっくりしたが、もう切ってきてしまったものはどうしようもない。親切心での行為であり、地元の人にとっては昔から普通にやっているあたりまえの感覚だったのだろう。まずいと知りながらもその材を使わせてもらった。ちなみに今回の新盛家の修復のために集めたオヒルギの材は、営林署の立ち会いのもとに伐採されている。鶏小屋の話に戻すが、そのオヒルギの樹皮を鉈できれいに剥がして使えといわれた。樹皮を剥がさないと虫が入り、ぼろぼろになってしまうそうだ。本当は海水につけるといいのだが、とも言っていたことも思い出した。まさにこの事だったのだ。その鶏小屋は確かに長持ちした。私がそれから5年後に横浜へ引き上げるまでの間、幾度も台風の風雨にさらされながらも、びくともしなかった。
村人たちが総出で茅葺屋根の茅となる植物を刈る
オヒルギを海に沈めてから、3ヶ月後にいよいよ新盛家の修復に必要な材料採りが本格的に始まった。まずは屋根に使う茅集めだ。ここで使う茅はチガヤというイネ科の植物のことだ。たくさんの人手が必要なので、村人たち総出の作業だった。以前は西表島の小島である外離れ島へ茅刈りに行っていた。島では野焼きをして、後に生えてきた新しい茅を使うこともあったそうだ。民具作りの時と同じで、素材の善し悪しの見極めが重要だ。茅ひとつをとっても古い葉はもちろん若すぎるものも使えないので、吟味して集められていた。
茅葺き屋根の家が多かった時代は、各家のメンテナンスのために多くの茅が必要だった。伸びては刈り取り、また伸びては刈り取るというように、人が常に利用することで、植物も更新されて良質なものが多く育ったそうだ。しかし、家がコンクリート造りになってからは需要はなくなり、それにともなって良質な茅が少なくなってしまった。
10年前の修復作業の時は、石垣島の平久保地区から一束200円で買ったそうだ。しかし、雨に濡れてしまったものや芯が折れて使い物にならない材料も多く、修復作業は難航したと聞かされた。
老若男女、世代を超えて新盛家の修復に一丸となる
一口に茅刈といっても、どのように茅を使うかで刈り方が違ってくる。老人から茅の刈り方を教わった。茅刈りはいわゆる雑草取りの草刈とは違い、手の中で束を大きくしながら刈る。右手でカマを持った場合、左手で茅をつかみ、押さえながら増やしていく。老人たちの作業を見ていると、ものすごく簡単にやっているが、いざ自分がやってみると、思うようにいかず、束の大きさにばらつきができてしまった。いつも思うのだが、見ているのとやってみるのとでは大違いだ。何事もやってみないとわからないとつくづく思う。
刈った束を3〜4束集めて、それをひとくくりにして大きな束を作る。家一軒の屋根を葺くためには、これを3800束作らなければならない。気の遠くなる作業だった。老若男女が入り乱れての作業は、年寄りが若い人に教え、若者は見よう見まねで覚えていく。老人たちはこの茅の束が次にどのような作業が行われ、どう使われていくのかを知っている。それを知らない若者たちは、先をイメージできずに作業をしている。きっと、次の行程へ進んだときにすべてがつながっていくのだろう。現代社会の中で失われていく光景が、ここにあった。老人たちと若者たちが新盛家の屋根を修復するという目標の下で気持ちがひとつになっていた。みんないい笑顔だった。
作業する村人同士の競争心が技術を磨き、知恵を生み、作業の効率を高めていく
茅を刈る作業だけでなく、運搬もやった。くくられた茅の束をかついで道路の近くまで運ぶ。いくつもの束を少しずつつかみ一気に肩に担ぐのだが、ぼくは片手に4束が限界で、合計8束を運ぶのがやっとだった。慣れた人は、15束ぐらいは運べるのだと聞かされたちょうどその時、全身を茅束で包まれた村人が目の前を通りすぎていった。確かに15束くらいは運んでいそうだ。まるで茅の妖怪のようでユーモラスな姿だった。
その姿を見ていて、以前に民具作りの取材で星さんから聞いた言葉を思い出した。それは、稲刈りの話だった。村人がみんなで作業していると、いつしか、誰が一番早く稲を刈ることができるか、誰が一番たくさん運べるかといった競争心が芽生える。その競争心から技術を磨き、知恵を絞り、結果的に作業の効率を上げることに結びついていったという。目の前を歩いている「妖怪カヤタバ」もきっとそんな風にして生まれてきたものなのだろうと思った。
山積みになった茅の束をトラックに積み込み、村の公民館へ向かった。刈った茅束は公民館に保管する。公民館に到着し建物の中を見た瞬間、猛烈な草の香りとともに思わず目を見張る光景が広がっていた。公民館にはすでに数日前に刈られた茅束が所狭しとおかれていて、ほとんど床かが見えない状態だった。茅束には扇風機がむけられ湿り気で駄目にならないように管理されていた。蛍光灯の光に照らされた茅束が扇風機の風で揺れている。
この日に刈った茅束を運び込むと、公民館の床は完全に埋めつくされた。