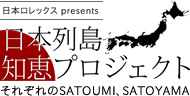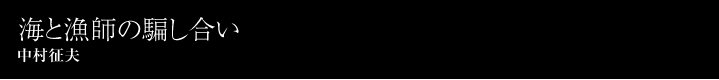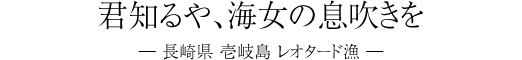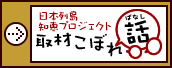![]()
2010.12.08
伝統の潜水漁をしているのはレオタードを着た海女?
玄界灘に浮かぶ壱岐島(いきのしま)は博多から70キロ。ジェットフォイルで約1時間の距離にある。
博多港を出た高速船は日本の歴史を遡るかのように、右手に志賀島、左手に玄界島を見ながら、北西に進路をとっていく。
この海に面した壱岐、そして松浦半島など九州北西部、五島列島には、同じような生活スタイルをもった海人(あま)族という人たちがかつて暮らしていた。
3世紀後半の中国の史書『魏志倭人伝(ぎしわじんでん)』にその暮らしぶりが記されている。
彼らは「好んで、漁鰒(ぎょふく)を捕らえ、水に深浅となく(深い浅いにかかわらず)、皆沈没して(もぐって)之を捕る………倭の水人は好んで沈没魚蛤(ぎょこう)を捕らえ、文身(いれずみ)をし、またもって大魚、水禽を厭(はら)う」
これは、魏の使者が朝鮮を通って、対馬、壱岐を経由し、松浦半島にやって来る間に実際に見た光景だろう。
壱岐島の東部・八幡(やわた)地区では今も海女が、古(いにしえ)の海人族からの伝統の潜水漁を営んでいる。しかも、レオタードを着て潜るのだという。
しかし、なぜ、レオタード──?
伝統漁とレオタードの組み合わせにたくさんの疑問符を浮かべながら、八幡に向かった。
若々しく、キュートな海女さんたち
8月5日。朝から茹(う)だるような暑さだ。宿から一歩外に出ただけでTシャツが汗みずくになる。ジージージージーとアブラゼミの鳴き交わす声が一層炎暑をつのらせる。午前7時40分。八幡浦漁港。海女さんを乗せる小舟がすでに漁の準備をしている。8時近くになると、三々五々、海女さんが港に集まってくる。早い船はすでに出港していった。ぼくらを目にとめた二人の海女さんが笑顔で手を振った。朝の太陽がぎらりと水面(みなも)を照らした。
そうするうちに、ぼくらの乗る船の海女さんたちも軽四や自転車に乗ってやってきた。片穂野八代子(かたほの・やよこ)さん(55歳)は壱岐東部漁協・海女組合会長である。小柄で若作り。とてもキュート。高齢の方が多いと聞いていたが、良い意味で、まったく予想に反していた。
他に2名の海女さん(赤木常子さん・65歳、酒井タツ子さん・65歳)が乗り、海士(男性アマ)が2名、そして船を操る船頭(片穂野さんのお兄さん)の計6名が船に乗り込んだ。
採りきれなかったアワビにはリボンで目印をつけておく
海に出ると、風が心地いい。
漁船のブリッジと舳先(へさき)の間に張った日除け用の青いテントを、風がはたはた鳴らして過ぎていく。
テントの下が海女さんたちの身支度や着替え、休憩場所だ。この船で生活しているような、どこか家船(えぶね)のような雰囲気。かつて船で暮らしながら海を旅した海人族のDNAがここにもあった。
「これ、何かわかる?」
片穂野さんがピンク色の洗濯ばさみをひょいと摘みあげた。洗濯ばさみの先には紐がつき、その先には浮子(うき)があり、ポリ袋で作ったビラビラした長いリボン。ピンク色のリボンも付いていて、そこには「叶大漁 アワビ・サザエ」と書いてあった。
「海底にアワビがいて、その場で起こせない場合はまた上がってこないといけないでしょ。そんなとき、アワビの周りにいるカジメにこの洗濯ばさみを付けてくるんです。リボンが目印になって、どこにアワビがいるかすぐわかるんです。昔は瀬が見えないほどカジメが生えていて、一度上がってくるとアワビの居場所がわからくなってしまうことがあったんです」
2~3年前から磯焼けがひどくて、カジメやアラメなどの海藻が少なくなり、アワビの量は減っているそうだ。
噛んだチューインガムで耳栓を固定
船は八幡半島をぐるりと回り、左京鼻を左手に見ながら、今日の漁場である金比羅神社の沖合に進んでいく。
揺れる船内で、片穂野さんが耳かきを始めた。
よく器用にできるもんだな、と不思議にも思い、感心もしていると、その横で同じような恰好で赤木さんが耳に綿を入れている。
「潮入らんごと耳に綿詰めて、その上から噛んだチューインガムを入れてひっつけてね。これせんと、鼓膜破れてしまうから」
耳かきを動かしながら、そう教えてくれた。
なるほど。そういうことだったのか──。
「私も耳壊してから、やりだしました。みなさん、鼓膜破ってますよ。これやると耳抜きいらないんです。
耳栓の綿は一番奥まで入れます。ガムを抜くときに綿も一緒に引っ付いて出てくるんです」
採りすぎ防止のために20年前から着はじめたレオタード
片穂野さんが言って、身支度を調えていく。 一番下にシャツ。そして長袖ハイネックのヒートテック。そしてまたシャツ。その上から水着、レオタード。計5枚の重ね着だ。
「準備に30分。耳栓入れて、ドリンク剤飲んで、目薬さしたりね」
水着とレオタードの間に、採ったアワビやサザエ、ウニを入れる。いちいち海に浮かべた桶まで入れにいかなくてすむように、こうしているのだという。
「ぴったりしてる方が動きやすいので20年前からレオタードを着はじめたんです。それまでは男物のシャツとパッチを着て、ブルマを穿いとった。分厚かったし、動きよかった。ここは昔からウエットスーツは着てはいけないんです。採りすぎてしまいますから。八幡の海女の仕事は5月1日から9月末まで。5月のアタマはほんと水が冷たい。氷水です。今日の倍くらいの服着て1時間か1時間半潜るのがやっと。水がだんだん温かくなって、泳ぐ時間が増えていくんです」
水着の肩紐に何か小さな白い木がぶら下がっている。
「お守りなんです。白南天の木に、般若経の文字を入れています」
南天?
「難を転じるから南天。魔除けの木です」
そう言いながらヨモギの葉で水中眼鏡を磨き、「叶大漁」と小さく書かれたフィンを履いて、ゆっくり海の中に入っていった。
お腹が徐々に膨らみ、身ごもったような姿に……
桶とともに泳いでいった片穂野さんは、見当をつけた場所までくると、やおら垂直に潜っていった。水中での無駄のない姿が美しい。あっという間に水深10メートルの海底に着くと、カジメの間を縫うようにして丹念にアワビを探していく。
ウニがいると素早く拾い上げ、アワビがいるとオコシガネで引き起こし、採ったものをレオタードと水着の隙間に入れていく──と、お腹が徐々に膨らみ、まるで海の幸を身ごもったような姿になっていく。
一回の潜水はおよそ1分。これを何度も何度も繰り返し、一潮(ひとしお・1ラウンド)約2時間半から3時間潜り続ける。
海女さんたちが海中から浮上する姿を見ていると、あちこちで「アアーッ」「ワーッ」、という声が聞こえてきた。
「今日も海に入れてよかったー」という声なのかと最初は思っていた。
が、見ているうちに、
──どうもそうじゃない……
と思い始めた。
先に船に上がってきた酒井さんが仲間の方を見遣りながら、教えてくれた。
「ボンベじゃないけん、疲れんめー。ほいで、海から出てきたら『ハーッ』て声が出る。そうすると、ちょっと気持ちが楽になるとたい。自然に出るとたい。息、長い人でも1分くらい。15メートルも潜って仕事して、また帰ってこんといけんけんね。海女さんで死んだ人、何人もおるとよ。石の下にアワビおるとき、そこに道具持っていって手のはさまって、出てこられんようになって…そういう人も昔おっちょってよ。今はおらんばってん」
仲間と自分の身を守るかけ声、「磯笛」
片穂野さんは18歳から海女の仕事をしている。子ども時代は海で遊びながらテングサを採ったりしていたが、海女になりたての頃はウニも貝も全く採れなかったそうだ。しかし徐々に潜れるようになって、1年目の秋には水深4~5メートルの所で仕事ができるようになった。
5月から6月中旬までは黒ウニ(ムラサキウニ)、その後は、赤ウニ、バフンウニ、サザエ、アワビを採る。今年、黒ウニはキロ1万円、赤ウニはお盆が近づくとキロ2万円、サザエはキロ530円くらい。ただ採れる量が年々減っているそうだ。
八幡では毎日二潮(ふたしお・2ラウンド)、6時間近く潜る。5月6月はまだまだ水も冷たい。海では何が起こるかわからないので、仲間の海女となるべく離れないように努めている。
「海から上がってくるときのアアーッていう声─磯笛というんですが─仲間がどこにいるか確認できるという安全確認にもなっているんですよ。海では何が起こるかわからない。だから、それぞれ魔除けを持っているんです」と片穂野さんが言うと、赤木さんが、
「私は自分の守り神様を指輪にしてる。福岡にある篠栗(ささぐり)さん。弘法大師さんの。あそこに年1~2回、『無事に海から上がらせて』と参らす人が多かった。お参りすると気持ちが何かちょっと落ち着くでしょ」
「ナミカゼトランゴト」は安全祈願、「シアセヨマンヨー」は豊漁祈願の呪文
八幡の海女さんは海に入る前に呪文を唱えるとも聞いたのですが──?
「『ナミカゼトランゴト』ち言うと。波風立たないで、自分の体に災いが及ばんようにと。そう言って船から泳いで行くとたい」
と赤木さんが言う。
「自分に対する掛け声というか。船の梯子おりてパッと海に入る前に、『今日もシアセヨマンヨー』と言いますね。『今日も漁がありますように。いっぱい桶に品物が入りますように』という意味です」片穂野さんも言う。
みんな、言ってるんですか?
「たいがい言うがですねえ」と赤木さん。
「私は言いますけど。人に聞こえんように、一人でそろーっと言う人もおるけん」と片穂野さん。
心の中で唱えるんじゃなくて、口に出して言うんですか?
「声に出さんと、神様には通じんじゃないですか。心だけじゃあね」
二人、声を揃えて言った。
その声の明るさが、壱岐の太陽のようだった。